夏目漱石『夢十夜』の第六夜を、ふと思い出した。
鎌倉時代の仏師・運慶が、護国寺の山門で仁王像を彫っている。ところが語り手の「自分」も含めて、大勢の見物人はなぜか明治の人間ばかりなのである。語り手には「古くさい」と見える当時の装束に身を固め、一心不乱に木を彫り続ける運慶。すると語り手の傍で眺めていた若い男が、運慶の見事な所作を賛美し、「木の中に埋まっている仁王を鑿(のみ)と槌(つち)の力で掘り出すのだから迷いもなく正確なのだ」と解説した。
それを聞いた「自分」も仁王が彫ってみたくなり、家に帰って片端から木を彫った。しかし仁王は出て来ない。「ついに明治の木にはとうてい仁王は埋まっていないものだと悟った」と、その最後部で漱石は「自分」に完敗を認めさせている。
漱石が『夢十夜』の連作を朝日新聞に書いたのが明治41年(1908年)の7月から8月にかけてであり、続く9月1日より、同じ朝日新聞に連載されたのが『三四郎』であった。その小説で漱石は、熊本から上京する三四郎の「これからは日本も発展するでしょう」という言葉に対して、同じ汽車の道連れとなった「髭の男」に「(日本は)亡びるね」とまで言わせている。
日露戦争の奇跡的勝利から3年を経て、遅れ馳せながら世界の列強に比肩しようとする日本は、漱石の目には揺らぐ礎石の上に建てられた速成の楼閣に映ったのかも知れない。重ねて推察すれば、巨艦や大砲は揃えても、鎌倉時代の仏師がなしとげた手業を明治近代の日本人が持てなくなったことを例として、ある種の巨大な後退感を作家は表現したかったのではないか。
人類の発展とは実は恐るべき退化であったことを、知る人と、知らない人が、夏目漱石から百年後の日本にもいる。
明確な結論を言えば、令和の木にも運慶ほどの仁王は埋まっていないだろう。
(埼玉S)

















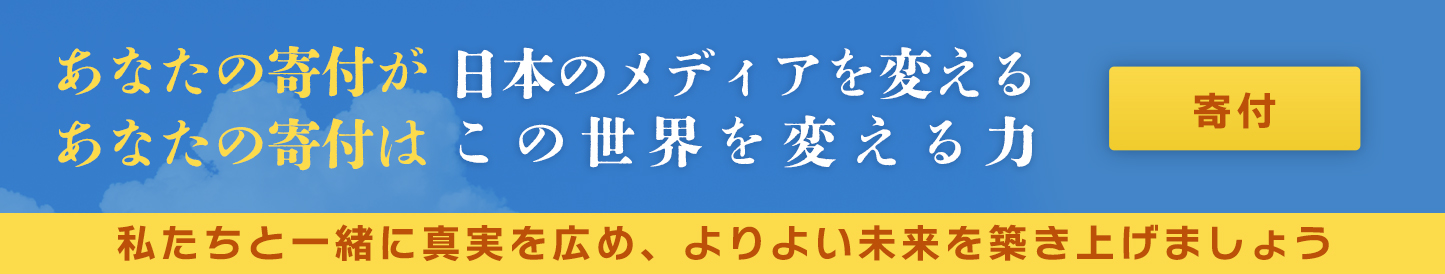
 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram



ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。