浅絳山水(せんこうさんすい)とは、水墨の輪郭と着色の上に、代赭色(たいしゃいろ)を原色として施した淡彩の山水画のことです。中国山水画の着色技法の一種であり、他のジャンルの山水画の基礎でもありながら、中国伝統絵画の中でも難度の高い技法の一つです。その方法は、濃淡、乾湿それぞれの墨で様々な輪郭線と構図を描いてから、淡い代赭色をメインカラーとして使用し、山石や木の幹を染め、最後に淡い花青色系で仕上げていきます。
清代に刊行された、古くからの歴代画論と技法を解説する彩色版画絵手本である『芥子園画伝(かいしえんがでん)』にはこのような記載があります。「黄公望(コウ・コウボウ)の皴の技法では、虞山(ぐざん)の山石をイメージして描写する。ほんのりした代赭色を着色に使用するのを得意とするが、時には代赭色の筆を使っておおよその輪郭も描く。一方、王蒙(オウ・モウ)は代赭色と藤黄色(とうおういろ)を山水画の着色に使用する。王蒙の作品では、山頂にバサバサと草を描き、代赭色で着色するのを好むが、時には他の色を一切使わず、代赭色で画中の人物の顔と松の樹皮を着色するだけである」。このような着色の技法は、五代十国時代の董源(トウ・ゲン)に始まり、元代の黄公望によって広まったもので「呉装山水(ごそうさんすい)」とも呼ばれます。
浅絳山水画は、木、石、雲水を主な描写対象としたもので、墨筆で輪郭を描き、淡い代赭色をメインカラーとして着色する、清楚で上品、澄み切った明快な技法を特徴とします。清代の画家・沈宗騫(シン・ソウケン)は『芥舟学画編』で「浅絳山水では、墨筆を基調とし、着色の加減をほどよくすべきである」と述べて、墨筆は画面上の物体構造の基礎であり、墨色が十分であれば、山石に少しだけ淡色を施すことで、画面の色彩をシンプルに統一することができ、色の濃淡のバランスをとれると主張しています。
浅絳山水画は、水墨山水画を基礎として淡い代赭色を着色する絵画です。肝心なのは、淡い代赭色と墨筆の輪郭線が強すぎないこと。もちろんその真意は、ある一定の形式に則して作品を完成するのではなく、その場の造化にしたがって自然な技法を用い、作品に命を吹き込むことにあります。
余談ですが、清末民初の頃に流行した一種の磁器があります。それは、黒を基調とする顔料に少量の調合油を入れたもので磁器の生地に山水画を描き、淡色などの顔料で着色してから、650~700度の低温で焼き上げる磁器です。このような磁器は、作風は浅絳山水画によく似ているため、「浅絳彩瓷(せんこうさいじ)」と呼ばれます。浅絳山水の文人画の淡麗さと清楚さを取り入れた浅絳彩瓷は、陶磁器文化に新たな発展をもたらしました。
浅絳山水画の創作にあたり、もう一つ注意する必要があるのは墨筆の使用法です。着色が淡いため、墨筆の書き損じを隠せないからで、これも他の山水画と大きく違うところです。中国伝統絵画の創作では、墨筆の「勾、皴、染、点」を重視します。勾とは、薄墨を使い物体の輪郭を描く技法。皴(シュン)は、山石、峰や樹皮の模様・木目を表現する技法です。染とは、色の筆と水気の筆を同時に使用し、色筆で着色したところを、水筆でにじませて濃淡を表す技法です。点は、点苔(てんたい)の事で、トンボがしっぽで水を打つように、筆で紙を軽く打ってすぐ離す技法です。この点と染を使って、景色の広がりをうまく表現することができるとともに、画面の奥行き感を増し、生き生きと、明確な風景を表現することができます。
また、墨筆の技法として溌墨(はつぼく)、積墨(せきぼく)、破墨(はぼく)、宿墨(しゅくぼく)、焦墨(しょうぼく)などの各技法があり、複数の技法を同時に使用することも可能です。浅絳山水では溌墨法に代赭色を使用することが多く、これは近代画家にも多用される技法です。迷わず、縛られず、大胆な筆遣いが求められますが、余白と物体の自然な変化に留意すれば、重い筆を使うことも可能です。
『黄山憶遊図』は張大千氏(1899年-1983年)が1956年に描いた山水画で、近代の浅絳山水の模範作とされています。この作品は、構図にゆるみがなく、筆遣いに勢いがあり、松の木が画面を横切る大胆な構図は唯一無二とされます。張大千は「皴擦り」の技法を用いて、薄墨で輪郭を描いてから代赭色を着色しました。極めて放逸な表現をみせる松の木は早期の張大千が模倣していたころの筆遣いですが、背後にある山石は、俊敏でありながら雄健な筆遣いであり、1950年代における張大千の画風の転換が伺えます。その画風は、石濤(セキ・トウ)などの画家の画風に縛られず、ますます円熟していきました。同作品は墨筆の情緒もありながら、素朴な気韻も備えており、まさに世にも稀な逸品です。
(文・戴東尼/翻訳・常夏)
(看中国より転載)
















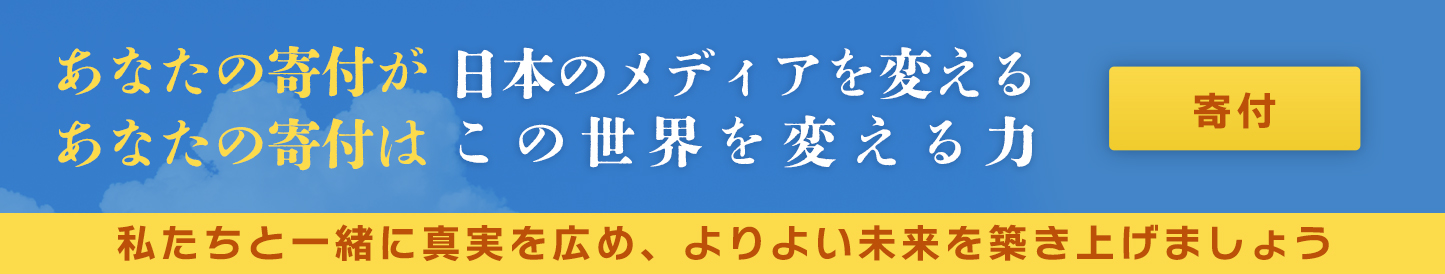
 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram









ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。