「帝は帝にならず、王は王にならず、千乗万騎は北邙山を追い駆ける。」
これは、『三国志演義』に最初に登場した童謡です。漢霊帝の死後、最後の二人の皇帝の運命を予言しています。作者は童謡をもとにして、天意の存在を暗示しながら、物語の展開を進めています。
一帝一王、帝王の宿命にならず
中平(後漢霊帝の年号)6年4月(189年)、霊帝は重病を患って、皇太子を立てず、後継者を指定する明確な辞令を残さずに亡くなってしまいました。権力を握る宦官たちは、霊帝が生前に望んだように、妾が生む子である劉協を皇帝にしたいと考えていましたが、霊帝の長男である劉辯の母親は正統な国母である何皇后です。
ですから劉辯には国の軍事力を司る大将軍である叔父の何進がついていました。劉協を王位につかせるためには何進を排除しなければなりません。宦官たちは、何進を宮中に勧誘し、隙を見て彼を殺そうと謀りました。その結果、計画が漏れてしまい、何進は宦官を一掃しようと決心しました。
何進は、すべての官吏を率いて、霊帝の霊前で、少帝である劉辯の即位を協力し、そして、少帝の母である何皇后に宦官を皆殺しにしたいと伝えましたが、何皇后に却下されました。その後、何進は袁紹の助言を聞き、外臣を募って軍隊を洛陽に導き、宦官を根絶するのを助けるようにと明確な命令を下しました。
これで西涼の刺史だった董卓が大軍を率いて洛陽に攻め込むことができました。本来、外臣の率いる軍隊を都に導くことは、非常に危険な行為で、いつの時代の皇帝も避けていました。そのようなことが許されたら、自分の政権が奪われる可能性は高いからです。そのため、皇帝の勅命がなければ、禁止令を破ることはできませんでした。
あえて破ってしまったら、軍隊が出発した途端に反逆者として摘発され、都に近づくことは一切できなくなってしまうのです。董卓がいくら野望を持っていたとしても、安易に出動することはできないため、皇帝や大臣を脅して若帝を廃嫡する機会もほとんどなかったのです。だからこそ、何進の行動は、董卓に千載一遇のチャンスを与えたと言えるでしょう。
盧植、曹操と他の大臣らが、いくら説得しても、何進は聞く耳を持たず、自分の望むように独断専行していました。尚書である盧植は、何進とは志が異なっているのに気づき、辞任しました。
その事を皮切りに、朝廷では、半数以上の官吏が辞任しました。董卓は朝廷を制御する準備ができ次第、首都に軍隊を率いて、命令を従わせるように官吏を拉致しました。同時に、張譲をはじめとする宦官たちは、自分たちの命が危険にさらされていることを察知し、先手を打ち、何皇后を利用して何進を宮殿内に勧誘し、部下に待ち伏せさせ彼を殺害しました。
それを知った袁紹は、軍隊を率いて宮殿に入り、宦官を皆殺しにして、宮殿を焼き払いました。宮殿は大混乱に陥っていました。
その後、張譲等の宦官たちは、逃げるために、少帝とその弟である陳留王の劉協を拉致して、北宮を離れ、夜遅くにはるばる北邙山まで逃走しました。途中で混乱し、少帝と劉協は迷子となり、宦官たちと別れてしまったので、彼らは川辺の草や茨の中に隠れていました。
その時、漢少帝は14歳で、陳留王は10歳にもなっていませんでした。兄弟二人は服が濡れ、飢えと寒さと痛みに耐えて、大きな声を出すことができず、戊夜(午前三時〜五時)まで辛抱していました。その後、民衆に助けられ、官吏と軍隊に守られて都に戻ってきました。
原作では、この時に童謡が登場しています。洛陽の子供たちが歌っているのは、「帝は帝にならず、王は王にならず、千乗万騎は北邙山を追い駆ける」です。この童謡は、予言として、本当に実現しました。
このように、洛陽の童謡は、事件の起こる前に予告したものになりました。しかし、誰もその真意を知らず、皆は事件があった後になってようやく予告であったと気付きました。その童謡の意味は、皇帝は皇帝らしくなく、王は王らしくなく、大臣と将軍たちは、拉致された皇帝を探すために、千乗万騎で北邙山を追い回していたということです。
帰宮後に、皇帝の権威の象徴である玉璽が無くなりました。童謡の予言では、劉辯がまもなく王位を失い、劉協が最後の皇帝になりますが、誰が皇帝になっても、実権を持たない名ばかりの存在になる運命にあるということです。「帝は帝にならず、王は王にならず」は、この意味なのです。人々が童謡の真意を理解したのは、事件を経た後のことです。
子どもの歌である童謡が予言になるとは、不思議に思われる人も多いでしょう。実際、周代には、現在と全く異なる意味で童謡を定義した歴史家がいました。
予言となる童謡 君主を警告し、未来を予告する
「天は人間の王たちに警告するために、『熒惑』という星を子供に変身させるように命じて、子供たちが学ぶための予言を作り、それが童謡と呼ばれた」(『東周列国志』による)「熒惑」とは、災星と考えられる火星です。この定義は、東周時代の太史である伯陽甫によって説明されています。古代の人々は、出所や由来の分からない子供たちが歌う童謡は、天の意志を代表し、将来の災いを予言するものだと信じていました。
童謡は君主への警告であると同時に、天に代わって世間の行く末や人々の運命を予言する不思議な力を持っているとされました。明らかに、童謡に出てくる予言は、ほとんどが災難等、極めて不吉なものです。後漢時代の童謡は、『三国志演義』に8回も登場し、警鐘を鳴らしています。それに何回も実現しているため、人々を驚愕させました。
実際、『三国志演義』に登場する童謡の半分は歴史書に記録されています。例えば、董卓が漢少帝を退位させた後の死を予言した有名な童謡「千里草,何青青,十日卜,不得生」
(千里の草はなぜ青々しているのか、十日ト、生を得られず)です。『後漢書』の解釈では、「「千」「里」「草」は合わせると「董」となり、「十」「日」「ト」は「卓」となる」「天意は曰く、下剋上、臣下として国王を凌いだ董卓は、権力を持っているように見えたが、すぐに滅ぼされて死んでしまう」と説明しています。この童謡は天の意志を予言していました。
中国古代の歴史書がフィクションではなく、天の意志の存在を明確に記録していることは示されています。また、童謡が支配者にも大臣にも「不義理をすれば悪に報いられる」と警告していることが分かります。このような神伝文化の歴史観に基づき、著者は『三国志演義』の物語を構想し、推進しているのです。義は自然に形成されたものではなく、神が伝えた真理にかなったもので、人間を規制するためのものです。正義を逸脱すれば、天罰が下ります。
『三国志演義』を見て 『紅楼夢』を理解する
実は、神伝文化の観点から発想されるものは、『三国志演義』だけではなく、『紅楼夢』といった四大小説も同様です。原作冒頭の第一話に注目すると、天意の存在について明示的に書かれていて、人間界で起こる出来事は、テーマが違うだけで天意と密接に関係していることが分かります。
例えば、『紅楼夢』は、世間の物事は幻影しかないと、幻を悟るように修道を勧めるものです。主人公である賈宝玉の周りの姉妹の運命を通して、人間社会の名声と富と情を見抜き、人間の世界は天に定められている演劇にしかないことを示しています。
これによって、人々に修道の道を呼びかけて、苦しみの海から抜け出すように勧めています。原作の第一話で、この物語の起源を説明しています。それは、女媧が天を繕った時に残った巨大な石は、地上に降りてからの経験を語っています。そこから始まった物語です。
この地上に降りてきた石は、転生した賈宝玉でした。彼は、人間世界を慕うがゆえに、自分を地上に連れていって輪廻転生させてほしいと、高僧と道士に懇願しました。それが終わると青埂峰に戻り、人間世界での経験を言葉にして石に刻むつもりでした。将来、自分の経験を書き写して人間界に伝えてくれる、縁のある人との出会いを願っていました。
これこそが人間界への旅の真の意味です。その結果、道を求めている「空空道士」が訪ねてきて、石に刻まれた言葉を書き写して、人間界に持ち込んだのです。このような経緯があったのです。
この空空道士は、その言葉を読んで、世間の因縁や運命、情愛を見抜き、悟りが開き、得道したのです。人と人とは、どんな関係であっても、それは結局、恩讐と人情のやりと返しだけのことです。その因縁が終われば、それぞれが自分の道を歩むのだと悟りました。
そして、女主人公の一人である林黛玉は、宝玉が天上にいたときに受けた灌漑の恩を返すために、石を追って地上に降りてきた者です。そのために一生の涙を流し、思い通りにならない人生を送っています。
しかし、『紅楼夢』は絶対に愛の悲劇ではありません。著者の目的は、宝玉が地上に降りてきた経験を通して、人々に、宝玉の姉妹に課せられた運命を理解させて、最終的に修道の道を奨めることにあります。
この作品には修道の真意が含まれています。著者の考えでは、宝玉は天から来た数百万人の中の一人で、人間界に迷い込んだら輪廻転生の苦しみを味わえることしかできず、これこそが無限の苦しみの海です。
したがって、古代の小説を読むときには、冒頭を読むことが大切です。作品全体には、天の意志や神の存在、世間の運命等が示されることが多く、人々に啓発を与え、開放感や神秘性を感じさせます。
彼らは皆、作品を通して道を説き、人々に修道の道を勧めたり、義理を守ったり、徳を重んじたり、善行をしたりするように助言します。このような考えを伝えることは、古代の学者の基本的な素質です。こういった小説が中国の歴史において有名になったのは決して偶然ではありません。
二人の皇帝が苦境に立たされた後、都に入った董卓は、その機会を利用して宮廷を掌握しましたが、何進の必要とする役割を果たすどころか、若い皇帝を退位させてしまいました。
(続く)


















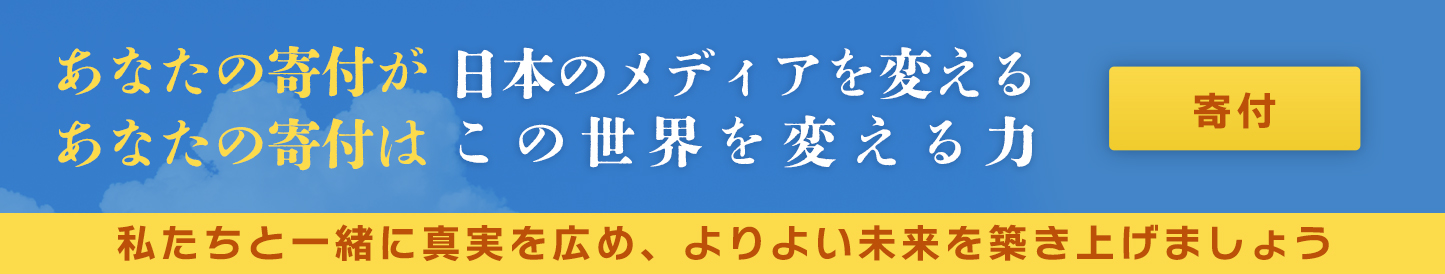
 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram









ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。