歴史上の賢明な皇后といえば、多くの人が唐の太宗の長孫皇后や、明の太祖の馬皇后を思い浮かべるでしょう。しかし、魏の武帝・曹操の妻である卞皇后については、あまり語られることがありません。おそらくそれは、『三国演義』に描かれた曹操がもつ奸雄のイメージがあまりにも強く、人々が曹操とその家族に対して多くの誤解を抱くようになっているためでしょう。だが、歴史をひもといてみれば、卞皇后の賢徳と先見の明は、歴代の名だたる賢明な皇后にも匹敵するものであることがわかります。
卞氏はもともと歌や舞を披露する歌妓であり、古代においては身分は高くはなく、卞皇后と呼ばれるようになったのは曹操の死後です。20歳のときに曹操の側室として迎えられ、その後、曹操とともに洛陽へと移りました。当時、董卓が乱を起こし、曹操は董卓に与することを拒んで名前を変えて洛陽を逃れました。その際、袁術が「曹操に身に何かあったのかもしれない」という知らせを送ってきました。
そして、曹操に従っていた人々の多くが曹操を見捨てて離れようとしました。そのとき、卞氏は強く制止してこう言いました。
「生死はまだ分かりません。今日家に帰ってしまって、もし明日お姿を見かけたら、どんな顔をして会えばよいのですか? たとえ本当に災いが降りかかろうとも、一緒に死ぬことの何が苦しいというのですか!」(三国志)
卞氏の義に満ちた堂々たる言葉に心を打たれ、皆は曹操のもとにとどまることを決めました。
その後、曹操が義兵を挙げて董卓を討つこととなると、卞氏もこれに従って出征しました。卞氏は行軍の途中、戦乱に苦しむ民衆の姿を目にすると、特に白髪の老人を見ると必ず足を止めて声をかけ、絹布などを贈って慰めました。このことからも、卞皇后がいかに庶民への深い同情心を持っていたかがうかがえます。
ご存じのとおり、曹操・曹丕・曹植の三人は、歴史上で広く知られる「建安文学」を築き上げ、「三曹」と称されています。彼らが中国文学史に残した貢献は、決して消えることのない偉大なものです。そして、曹丕と曹植はいずれも卞皇后の子であり、彼らがこれほどの業績を成し遂げた背景には、母である卞氏の優れた教育が密接に関係していたことは明らかでしょう。
また曹丕が太子に立てられたとき、側近たちは卞皇后を祝福し、「宮中の財宝をすべて使って賜り物にしてはどうか」と勧めましたが、卞皇后はこう言いました。「王(曹操)は、丕が年長だからという理由で跡継ぎに選んだのです。私はただ、子どもたちの教育に誤りがなかったことを幸いに思うだけで、どうして重い褒美を与える必要があるのでしょうか!」(三国志)
大意は、曹丕が年長であったため太子に立てられた、私は子どもたちの教育に過ちがなかっただけでも幸いであり、他人(ここでは側近、つまり臣下・官僚・廷臣など、宮廷内部の関係者)に多くの褒美を与える理由などないということ。その言葉を側近が曹操に伝えると、曹操は卞皇后を称賛してこう言いました。「怒っても顔色を変えず、喜んでも節度を失わない。だからこそ最も難しいのだ」(三国志)卞皇后が怒っても顔に出さず、喜んでも分をわきまえて節度を保つという態度は、深い道徳的修養と広い寛容の心がなければ、とてもできることではありません。
卞皇后は曹操に仕えて四十年以上、その後に王后に封じられてからも、生活は非常に質素でした。彼女の部屋には金銀の豪華な装飾などはなく、ただ黒漆で塗られたごく普通の器物が置かれているだけで、朝廷の支出を抑えるため、彼女は自ら進んで「食事を減らし、金銀の器をすべて廃止するように」と申し出ました(古今図書整合)。また『太平御覧』には、「太后の身の回りでは、野菜と粟飯のみで、魚や肉はなかった。その倹約ぶりはこのようなものであった」と記されています。書中の言葉はわずかですが、贅沢が手の届く地位にありながら倹約を守るというのは、たとえ古代であっても極めて貴重な美徳でしょう。
卞皇后は自分自身が倹約を実行するだけでなく、親族にも厳しくそれを求めました。彼女は親戚たちに対してこう言っています。「暮らしにおいては節約に努めるべきであり、恩賞を期待してはならない。自分の身を誤ることを思いなさい」(古今図書整合)
またもし親戚が法を犯した場合は、むしろ重く処罰するとし、「法に触れた者には、私は一段重い罪を加える。金銭や食糧の恩赦など望んではならない」(『資治通鑑』より)と述べています。歴史上でも現代社会においても、多くの皇帝や高官が妻やその親族との関係に苦慮してきましたが、卞皇后のように大義を深く理解している姿勢は、まさに感嘆に値します。これほどまでに信頼に足る人物だったからこそ、曹操からも深く信任されたのでしょう。
建安25年(西暦220年)、曹操が病没し、同年に曹丕が禅譲を受けて即位、皇帝となりました。そして曹操を「魏武帝」と追尊(死後に尊んで称号を贈ること)し、卞氏は「皇太后」となりました。一度、曹植が罪を犯し、大臣たちから弾劾され、魏の文帝・曹丕は、母の卞皇后が末子の曹植を特に可愛がっていたことをよく知っていたため、すぐに処分を決めかね、卞皇后の甥である卞蘭を通じて母の意向を伺おうとしました。しかし、卞皇后は私情から曹植をかばうことなく、曹植が罪を犯したことをただただ嘆いただけでした。彼女は卞蘭にこう伝えさせました。「私のために国の法を破ってはならない」(三国志)また、曹丕に会っても、卞皇后はこの件には一切触れようとしませんでした。
卞皇后は政治に干渉することはありませんでしたが、曹丕の政道に誤りがあったときには、毅然とした態度を見せました。かつて曹丕が若い頃、親戚の曹洪に絹を借りようとして断られたことを恨みに思っており、即位後、曹洪の食客の罪を理由に、曹洪を投獄し死刑を宣告しました。これを知った卞太后は激怒し、曹丕を厳しく叱責してこう言いました。「梁と沛の間において、子廉なくして今日はなかった!」(資治通鑑)ここでの「子廉」は曹洪の字(あざな)であり、卞皇后は、かつて曹洪が命がけで曹操を救ったことを忘れず、その恩を思い出すよう曹丕に諭したのである。さらに卞皇后は、曹丕の妻である郭皇后にこう言い放った。「もし曹洪が今日死ぬことになれば、明日には皇帝の勅命で皇后を退位させる!」(資治通鑑)
郭皇后は恐れて何度も涙ながらに曹洪の助命を願い出たため、最終的に曹洪は救われました。卞皇后は恩に報いる心を持ち、曹洪を救うために素早く決断し行動し、その姿勢はまさに毅然たるものであり、美談として語り継がれるにふさわしいものだったのです。
曹植はかつて母・卞皇后を讃えて、こう述べました。「地(坤)の本源の性質を備え、万物を包み込む仁徳を体し、姜嫄(きょうげん)と美徳を並べ、任姒(じんし)と徳を等しくし、内廷にて政(まつりごと)を補佐し、その恵みは四海にまで及ぶ。草木でさえその恩に浴し、あらゆる命はその潤いを受けて育つ。願わくは最上の吉祥が満ち、万代にわたりその地位と恩徳が継承されんことを」(曹子建文集・卞太后への誄表(るいひょう))
訳)
「大地のように広く深い徳を備え、あらゆるものを包み込む慈しみの心を身をもって示し、その美徳は古の賢婦・姜嫄(きょうげん)に並び、任姒(じんし)にも肩を並べるものだ。皇后として後宮(内廷)にいながら、皇帝の政治を内側から支え、その恵みは天下四方にまで及んだ。草木でさえその恩に潤い、あらゆる命がその徳によって育まれている。願わくは、最上の吉兆が常に満ち、その地位と恩徳が末永く受け継がれてゆきますように」
卞皇后は、曹操の賢き内助として仁愛と徳を備え、大義を深く理解し、戦乱の世においても子どもたちを立派に育て上げました。 まさに閨中(妻のこと)の模範たる存在であり、歴代の賢明な皇后にも匹敵する人物です。
――正見ネットより転載



















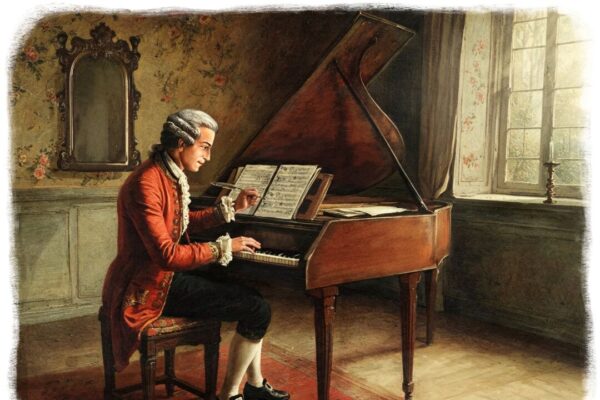




 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram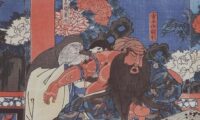





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。