空間認識における相対
これまでの内容を読んできて皆さんは、あることに気づいたと思います。それは、視点の基準が変わると、宇宙空間における方向の識別も変わるということです。
蘇軾は「題西林詩」の中で「横看成嶺側成峯、遠近高低無一同」(視線を横に動かせば山脈となり、側から見ればそそり立つ。遠い場所に近い場所、高い場所に低い場所、どれ一つ同じ姿はない)と述べています。我々の空間に対する認識には常に相対的関係が伴っています。
つまり、南極に立っている人が言っている方向と、北極に立っている人が言う方向は真逆なのです。最も身近な例として、向かい合っている相手に右の方向を示す時、相手に左と勘違いされることはありませんか?
絵画においてこの相対的関係を理解することは非常に重要です。例えば、大型壁画によく見られる天井画は、マルチアングルから構図を考えなければなりません。観客は様々な角度や立ち位置から天井画を鑑賞するため、画家は様々な角度から鑑賞されることを想定して、遠近法を運用しながら構図を考えなければならないのです。

遠近法は視覚における空間認識の相対という基準の上で成り立っています。簡単に説明すると、ある物体がその人の近くにある時、たとえそれが1枚の葉っぱであっても、その人に大きく捉えられます。しかし、その反面、あるものがその人から離れた場所にある時、たとえそれが山であっても、小さく捉えられるのです。
「目の前の一部の現象に惑わされて物事の本質が見えなくなる」ことがまさにこの規則性に従っています。遠近法の中ではこれを「遠小近大」と呼びます。しかし、これらの原則にはある前提がありますーーこれらはすべて人間がいるこの環境内の規則であり、この範囲を超えると全く別物になるのです。
例えば朝の太陽は大きく見えるが、昼間の太陽は小さく見えます。これは透視図法の遠小近大の原則に合わなくなります。また、空間の屈曲や光の状態など宇宙で起こり得る様々な状況により、天文望遠鏡を通じて遥か遠く離れた天体を観察する時、遠大近小のような虚像が発生することもあるのです。
つまり、人間の理論は人間が存在しているこの空間内、範囲内でしか通用せず、この範囲を超えると、全く別の概念になるのです。
(つづく)
(翻訳編集 華山律)

















 絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(一)
絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(一)  絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(二)
絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(二)  絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(三)
絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(三)  絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(四)
絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(四) 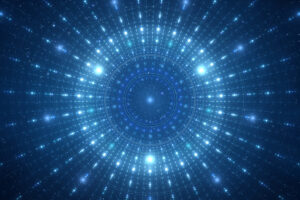 絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(五)
絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(五)  絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(六)
絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(六)  絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(七)
絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(七)  絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(八)
絵の中の時空ーー美術家=物理学者?(八) 






 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。