自然農法という言葉は、日本発祥とはいえ、まだ100年ほどの歴史しかない。また、明確な定義もない。日本では、古くから人糞肥料を使う習慣があり、さらに明治時代になってから化学肥料や農薬を使うようになったことで、農地が荒れ、不健康な農作物が一般に広がるようになっていた。そんな環境のなか、2人の先駆者が現れた。ひとりは岡田茂吉、もうひとりは福岡正信という。それ以来、多くの有志がどちらかの考え方を学び、研究と実践を続けている。
肥料や農薬に頼らずとも農作物は栽培できる──。2人の先駆者は同じように持論を提唱した。そして、その理想に人生をかけた人たちが少なからずいた。この記事を書いている私自身もそのひとりだ。しかし、自然農法はいまだに世間に広く認知されておらず、途中で挫折する実践者も後を絶たない。ところが、20世紀後半から21世紀にかけての数十年、科学の発展はすさまじいものがあった。人間は月に旅行に行ける技術を発明し、庶民がインターネットによって瞬時に情報を交換することも可能になった。その重要な鍵を握っているのが量子物理学(量子力学、量子論ともいわれる学問分野)だ。

一般には馴染みのない言葉であるし、その考え方を理解するには、少なからず科学の知識が必要になる。ただし、ふだん私たちが使っているスマートフォンやパソコン、テレビやDVDプレーヤーなどの心臓部である半導体(ICやLSIといった集積回路)は、量子物理学を応用した電気製品であることぐらいは知っておきたい。そして、量子物理学は近年、さらに奥深い研究成果が一般にも知られるようになったことで、実は自然農法も新しい局面を迎えている。つまり、これまで抽象的な理想論でしかなかった技術が、科学的な説明で裏付けられるばかりか、再現性も示すことができるほど進化しているのだ。

いまの農業技術は、農作物を育てるのに肥料(養分)が必要だという。ほぼすべての研究者は、肥料栽培を前提にしている。そして、だれが、どれほど研究を重ねても、健康な農作物を栽培できる技術に高めることができず、弱点を補うため常に農薬に頼ることしかできていない。それどころか、肥料栽培の技術革新に目途が立たないことから、病気や虫食いに強い遺伝子組み換え品種の開発に舵を切っているのが現状といえる。そしてそのことが、地球環境を破壊していることは、だれも否定できないだろう。
一方、自然農法の考え方は極めて単純だ。私たち人間が地上に現れる前から、植物は地上に繁殖して豊かな森を作っていた。舗装道路に植えた街路樹は、だれも肥料を入れないのにすくすく育つ。庭に生えている柿の木は、放っておいても美味しい実をつけてくれる。この地球には、植物が自然に育つ仕組みがそもそも存在している。その仕組みを、農作物の栽培に応用すれば良いだけのことではないか。

いま、100年前にはなかった情報が2つある。1つ目は、微生物が関係しているということ。そして2つ目は、微生物や植物が土の成分を変化させているということだ。そもそも地球には、何種類の植物が生息しているのだろうか。専門家によれば、数十万から数百万種類だという。では、微生物の種類はどうだろう。こちらも数十万から数百万種類に上ると言われている。つまり、我々人間は、植物のことも、微生物のことも、まだ完全には理解できてはいない。しかし、植物と微生物が密接にかかわり、むしろ表裏一体の生き物であることが分かってきている。
私たち人間も、腸内細菌や皮膚の常在菌との共生関係を持つ。あるいは、昆虫や爬虫類、多くの哺乳類を見渡すと、実はすべての動植物が微生物と共生関係にあることが分かる。この点に注目していないばかりか、殺菌剤を使ってあらゆる微生物を殺す現在の農業技術は、時代遅れと言っても過言ではないだろう。
植物は、光合成によってブドウ糖をつくっている。材料は水と空気だ。そして、ブドウ糖を根っこから放出している。根の周囲にいる微生物たちがそのブドウ糖をエネルギーとして受け取り、土を溶かしてミネラルを抽出したり、空気からアミノ酸を合成したりして、植物に供給していることが分かってきた。さらに興味深いのは、土壌に足りないミネラルは、微生物や植物が「元素転換」をして創り出していることも、ほぼ間違いないと推測される。
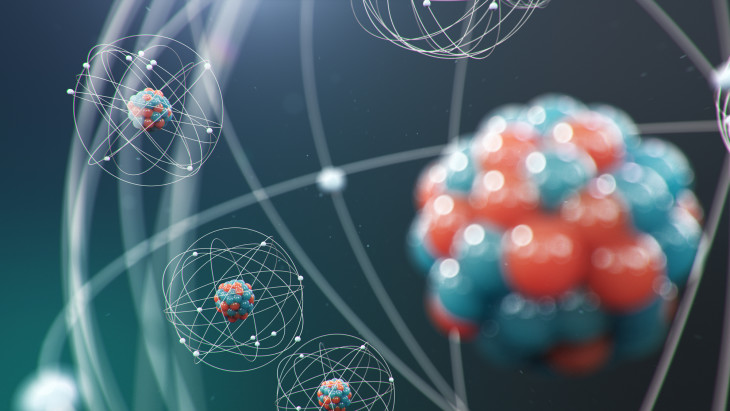
元素転換は、フランスの科学者、ルイ・ケルヴラン(1901 -1983年)が唱えた学説で、動植物の体内でつくられる酵素や、微生物の働きによって、核融合や核分裂のような反応「元素転換」が日常的に起きているという。たとえば、痩せた土地に生えるスギナについて調べたところ、カルシウムが乏しい土壌のはずなのに、スギナに大量のカルシウムが含まれるのは、土壌中のケイ素と炭素が融合して、カルシウムになった証拠だという。ほかに、さまざまな調査によって、イオウ、マグネシウム、カリウムなどが土壌中でつくられているという報告もある。

ひと昔前なら、見向きもされなかった学説であるが、土壌検査によって肥料分が計測できない農地で、スイカや大根、小松菜などの大量生産に成功している私にとっては、元素転換が実際に起きているとしか解釈できなかった。そして、原子を構成する量子についての研究が進んでいる今、元素転換はもはや当たり前のことであり、量子物理学を組み入れた農科学者が、人類の未来を切り開くキーパーソンなっていくと信じている。
つづく

※無断転載を固く禁じます。

















 1. 人口爆発と肥料栽培の限界~資源は枯渇する
1. 人口爆発と肥料栽培の限界~資源は枯渇する  2. 栄養学のパラダイムシフト~素材の安全性はどうなのか
2. 栄養学のパラダイムシフト~素材の安全性はどうなのか  3. がんの原因は肥料と農薬~石油由来の毒に注目せよ
3. がんの原因は肥料と農薬~石油由来の毒に注目せよ  4. 自然農法の歴史と現在~量子物理学が農科学を進化させる
4. 自然農法の歴史と現在~量子物理学が農科学を進化させる 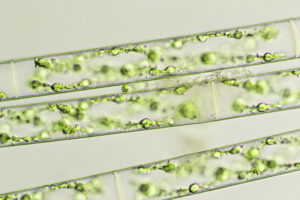 5. 植物と微生物の共生関係~すべての生き物が微生物と共生している
5. 植物と微生物の共生関係~すべての生き物が微生物と共生している  6. Halu農法~完全自然農法への道
6. Halu農法~完全自然農法への道  7. 肌がきれいになる農作業~善玉菌が全身を浄化する
7. 肌がきれいになる農作業~善玉菌が全身を浄化する  8. 自給自足は可能か?~消費者から生産者の目線へ
8. 自給自足は可能か?~消費者から生産者の目線へ  9. 病気にならない子供たち~免疫力を鍛え上げる
9. 病気にならない子供たち~免疫力を鍛え上げる  10. 人生の本当の喜びを得る~自然界とリンクする
10. 人生の本当の喜びを得る~自然界とリンクする  11. 子供の知性と運動能力~農場で得られる効果
11. 子供の知性と運動能力~農場で得られる効果  12 人口200億人まで養える~自然農法で砂漠を農地に
12 人口200億人まで養える~自然農法で砂漠を農地に  ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram


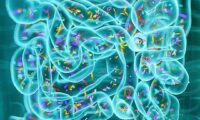


ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。