生理痛とは、月経の際に起こる痛みのことで、主に骨盤や下腹部に起こる事が多く、腰痛や下痢、吐き気などを伴うこともあります。症状は月経が始まると痛みが現れ、通常は3日以内に治まります。中医学では、患者の体質や生理痛のタイプ、関連する症状に応じて、適切な治療法を選びます。主な方法として、漢方薬による体調管理、鍼灸療法、薬膳を取り入れた食事療法などがあります。
6種類のよく見られる生理痛―中医学による症状別治療
1. 気滞型の生理痛:痛みは腹部の側面や下腹部に起こりやすく、張るような痛みが特徴です。月経血の流れが悪く、胸や脇に張ったような不快感を伴うことが多くあります。舌の色は赤黒く、脈は弦が張りつめたようになります。
情緒が不安定で、肝気が滞りやすい体質の人に多く見られます。
【よく使われる処方:逍遥散】
2. 気血虚型の生理痛:痛みは下腹部にじわじわと続き、重だるい感覚を伴います。お腹を温圧すると楽になるのが特徴です。月経血の量は少なく、色も淡いです。腰のだるさや足の力が抜けるような感覚、肌のくすみ、声が低い、舌の色の薄さ、脈の弱さといった症状がみられます。普段から気血が不足している人や、大病・長期療養の後で気血が足りなくなった人に多く見られます。
【よく使われる処方:血虚には桃紅四物湯、気血両虚には八珍湯を加減して使用】
3. 虚寒型の生理痛:お腹が張るような痛みがあり、月経量は少なめで、塊になっていることが多いです。下腹部が冷えやすく、手足が冷たくなることが多く、舌苔は白っぽく、脈は細く弱いのが特徴です。体内の陽気が不足し、寒さを感じやすい体質の人に見られます。
【よく使われる処方:温経湯を加減して使用】
4. 血瘀型の生理痛:生理前や生理中に下腹部に鋭い刺すような痛みを感じ、押さえると痛みが強くなるのが特徴です。月経の色は紫黒色で、血の塊が混じることが多く、塊が出ると痛みが和らぎます。舌の色が紫がかっていたり、瘀斑(血の滞りによる斑点)があったりすることが多くみられます。脈は弦脈またはざらついた感じのある渋脈になります。血の巡りが悪い気虚血瘀体質の人に見られます。
【よく使われる処方:少腹逐瘀湯】
5. 寒湿凝滞型の生理痛:生理中または生理後に、下腹部が冷えて痛む、またはけいれんするような痛みがあります。押すと痛みが強くなりますが、温めると和らぐのが特徴です。月経の流れが悪く、量は少なく、色は淡めで、黒豆の汁のような暗色の塊を含むことがあります。その他、寒がり、大便がゆるく形が定まらない、舌の縁が紫色、舌苔が白く粘つく、歯茎が暗紫色を帯びることもあります。湿気の多い場所に長く住んでいる人や、生理前に水に浸かったり、雨に濡れたり、冷たいものを摂りすぎたりすることで、寒湿が子宮に入り込み、血が滞ることが原因となります。
【よく使われる処方:温経湯】
6. 肝腎不足型の生理痛:下腹部が痛み、月経量が少なく、血の質が薄く色も淡いのが特徴です。腰や膝がだるく、疲れやすい、めまいや耳鳴りがするなどの症状を伴うことが多いです。舌苔は白く、脈は沈んで細く弱いです。これは、もともと肝腎の機能が弱い体質の人や、早婚・多産、性生活の不摂生などにより肝腎の精気が不足し、月経後に子宮の血管が十分に養われないことが原因となります。
【よく使われる処方:帰腎丸を加減して使用、または六味地黄丸や腎気丸を加減して使用】
これらの処方はあくまで参考です。具体的な治療法は、漢方医が個々の体質や症状に合わせて決定します。
生理痛の緩和―鍼灸療法は安全で効果的
漢方薬の服用に加え、漢方医は鍼灸を併用して治療効果を高めます。特定のツボを刺激することで、気血の巡りを整え、体内の陰陽バランスを調整し、臓器の働きを改善することで、痛みや関連症状を効果的に和らげます。
鍼灸療法は安全であり、効果も期待できます。患者の具体的な症状に応じて、適切なツボを選び、漢方薬と組み合わせることが重要です。一般的に、体質や病因、症状を総合的に判断し、個別に最適な治療計画を立てます。治療を受ける際は、必ず資格を持った漢方医に相談し、最大限の効果を得られるようにすることが大切です。
食事療法で生理痛を和らげる―中医学がすすめる薬膳
★ 益母草のゆで卵:すべてのタイプの生理痛に適応
【材料】益母草(マザーワート) 30~60g、卵 1個または3個(必要に応じて調整)、黒糖 適量
【作り方】
- 適量の水を用意し、益母草と卵を一緒に煮る。
- 卵がちょうど茹で上がったら殻をむき、黒糖を加えてさらに少し煮る。卵を食べ、煮汁を飲む。
【注意】
益母草や黒糖の量は、体質に応じて調整できます。糖の摂取が気になる場合は黒糖を使わず、麦芽糖や蜂蜜に代えることも可能です。冷えが強い体質の人は、乾姜やシナモンを加えるとよいでしょう。腎虚や血虚の人には、熟地黄や当帰を加えるのもおすすめです。
【効果】
血行を促進し、瘀血を取り除き、生理痛を和らげます。益母草はやや冷性で血行を良くする働きがあり、卵は体を温める作用があります。この組み合わせは、寒熱や虚実のどちらのタイプにも適しており、体を補いながらも滞りを防ぐことができます。
★ 桂円紅棗湯(龍眼とナツメのスープ):気血虚タイプの生理痛に適応
【材料】桂円(龍眼肉)、紅棗(ナツメ)、クコの実、水
【作り方】桂円肉、紅棗、クコの実を水と一緒に煮る。1日1~2回飲む。
【効果】気血を補い、体を養います。
★ 丹参紅棗湯(丹参とナツメのスープ):血瘀タイプ、生理血が不足し滞るタイプに適応
【材料】丹参、紅棗(ナツメ)、水
【作り方】丹参と紅棗を水と一緒に煮る。1日1~2回飲む。
【効果】丹参は血行を促進し、瘀血を取り除く作用があり、紅棗は気血を補う働きがあります。
★ 姜棗茶(生姜とナツメのお茶):寒湿凝滞タイプの生理痛に適応
【材料】生姜、紅棗(ナツメ)、黒糖、水
【作り方】生姜と紅棗を水と一緒に煮て、黒糖を加えて味を調える。1日1~2回飲む。
【効果】冷えを取り、子宮を温めて血行を促します。
★ 当帰生姜羊肉湯(当帰と生姜の羊肉スープ):寒湿凝滞タイプの生理痛に適応
【材料】(2~5日分)当帰 30g、生姜 30g、羊肉 500g
【作り方】
- 当帰(アンジェリカハーブティー)と生姜を洗い、スライスしておく。
- 羊肉の筋や膜を取り除き、沸騰した湯で軽く下茹でして血抜きをする。
- 茹でた羊肉を冷まし、一口大にカットする。
- 土鍋に羊肉、当帰、生姜を入れ、適量の水を加える。強火で沸騰させた後、アクを取ってから弱火でじっくり煮込み、羊肉が柔らかくなるまで加熱する。
【効果】血を補い、体を温め、寒気を取り除きます。当帰は血を補い、生姜は体を温める作用があり、羊肉は気血を補う効果があります。
★ 黒豆大棗湯(黒豆とナツメのスープ):肝腎不足タイプの生理痛に適応
【材料】黒豆 90g(12時間以上水に浸す)、大棗(ナツメ) 30g、生姜 3枚、水 適量、黒糖 適量
【作り方】浸水した黒豆、大棗、生姜を適量の水とともに煮て、粥状にする。最後に黒糖を加えて味を調える。月経開始3日前から1日1回、10日間続けて飲む。
【効果】黒豆は栄養が豊富で腎を補い、大棗は気血を養い、生姜は胃を温め冷えを散らす作用があります。これらを組み合わせることで、体の回復を助けます。
注意事項
薬膳を摂る際は、自身の体質や健康状態を考慮し、不安があれば必ず専門の漢方医に相談してください。
糖尿病の方は、糖分を含む薬膳を避けるか、適切な代替品を使用してください。
生理痛の予防―日常でできる7つのセルフケア
1. 情緒を安定させる:瞑想、ヨガ、深呼吸などを活用し、不安や緊張を和らげましょう。休息と活動のバランスをとり、適度な運動を心がけることが大切です。栄養をしっかり摂り、生活リズムを整え、十分な睡眠を確保することで、体の抵抗力を高めることができます。
2. 体を冷やさない:普段から冷えを避けることが重要です。雨に濡れる、水に浸かる、湿った場所に長時間座るといった行動は控えましょう。薄着や湿った衣服も避けるべきです。特に月経中は、体を温かく保つようにしましょう。
3. 夜更かしをしない:規則正しい生活は、体のバランスを保つのに役立ちます。夜はしっかりと睡眠をとり、できるだけ夜更かしを避けましょう。
4. 過労を避ける:長時間の連続作業や過度な肉体労働は控え、適度に休憩をとることで、体力を維持しましょう。
5. むやみに薬を飲まない:体が冷えやすい人や、脾腎の陽気が不足している人は、寒性の薬を避けましょう。逆に、体に湿熱がこもりやすい人は、過度に体を温めるような食材(乾姜、肉桂、附子など)を控えることが大切です。また、漢方の止血薬や収れん薬、西洋薬の凝血促進剤や止血薬は、痛みを悪化させる可能性があるため注意が必要です。
6. 月経中の性交渉を避ける:感染症や大量出血を防ぐため、月経中の性交渉は控えましょう。
7. 食事に気をつける
- 冷たいものや体を冷やす食べ物を避ける:体が冷えやすい女性は、月経中やその前後に、冷たい飲み物や体を冷やす食べ物を避けましょう。例えば、氷入りの飲み物、生野菜のサラダ、ほうれん草、きゅうり、クワイ、カニ、貝類、梨、スイカ、柿、バナナなどが挙げられます。
- 酸味の強い食品を控える:酸味のある食品(五味のうちの「酸」)には、収れん作用があり、血管を収縮させることで経血の流れを妨げる可能性があります。そのため、漬物、ピクルス、酢、青梅、いちご、レモン、スターフルーツ、さくらんぼ、ザクロ、サンザシ、プラム、杏などは避けたほうがよいでしょう。
- 刺激の強い食べ物を控える:一部の生理痛は、湿熱が子宮にこもることで引き起こされます。辛くて熱を持つ食べ物は、骨盤内の充血や炎症を悪化させる可能性があり、子宮筋が過剰に収縮して痛みが増すことがあります。そのため、タバコ、アルコール、ニラ、にんにく、唐辛子、胡椒などの刺激の強い食品は避けるのが望ましいです。
(翻訳編集 華山律)



















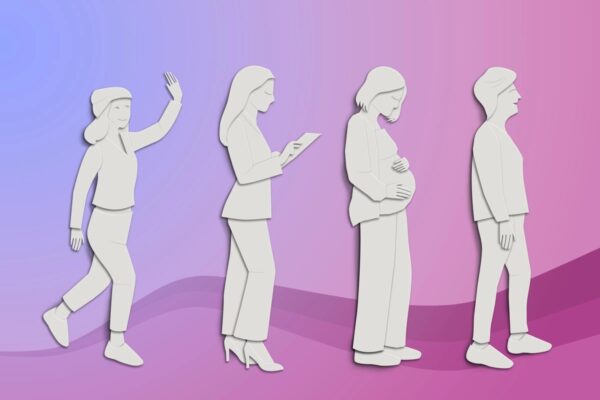




 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




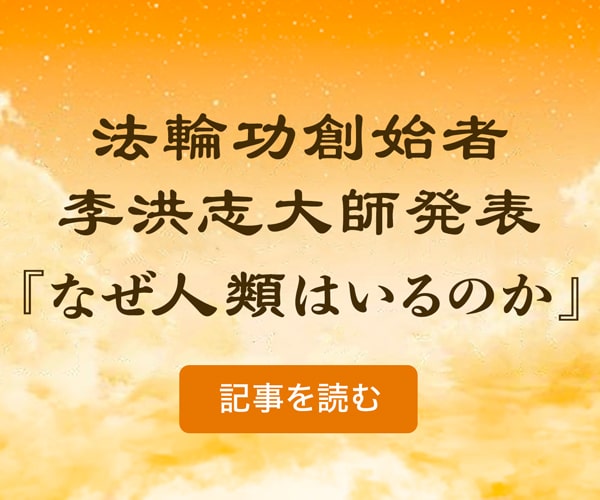
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。