ウェンシーが堡塁を七層まで建て終えた時、ある施主がマルバに灌頂を願い出てきたので、その儀式を執り行うこととなった。師母は心の中で思った。「この怪力君は一心に法を求めている。この灌頂の儀式に機会を借りて、師父に法を求め灌頂してもらえばいいわ」。そしてウェンシーに言った。「怪力君、あなたは本当によく働きました。この灌頂の儀式を借りて、あなたもついでに灌頂を受ければいいわ」
ウェンシーも思った。「ここ数年、私一人で山の上に多くの建築工事をしてきたが、いっぱいの泥、一杯の水も、誰一人の支援も受けなかった。このたびの大規模工事だって、さっそく順調に仕上がりつつある。師父だって、きっと私にも灌頂をしてくれるにちがいないぞ」
こうしてウェンシーは灌頂の儀式の時、師父を礼拝したうえで、さっそく灌頂を受けるその席上についた。師父はそれを見ると彼に尋ねた。「怪力!おまえは灌頂の供養をしたのか?」
「先生は、工事がうまくいけば、法を伝え、灌頂をして下さるとおっしゃいました。だからこうしてやってきたのです」
「きさま、供養もしていないのに、わしに灌頂を求めるというのか?」師父は怒って言った。「たかだか少しばかりの工事をしたぐらいで、わしがインドで死に物狂いで会得した口訣と灌頂をものにしようというのか?供養をしないなら、この席につくことは許さん!」
ウェンシーが灌頂の席につくかつかないかの間に、師父はつかつかとその面前までやってきて、掌でそのこめかみを張った。ウェンシーは痛みで両目から星が出て、失神しそうになった。師父はその頭髪を掴むと、その席上から引き摺り下ろし、門外にたたき出すと彼を蹴倒して言った。「さがっておれ!」
ウェンシーは門外に膝まずいて座ると、しばらくの間、どう反応していいやらわからなかった。ここ数年、彼が我を忘れて一心に建築に励んできたのも、法を早く得たかったためであり、そのため背中や腰に爛れた擦り傷があっても、休養をするいとまもおしみ、さらに痛みが走っても師母に愚痴をこぼすこともなかった。しかし、師父は法を伝えてくれなかったばかりか、却って侮辱し罵倒した。師父の勘気は知らないことはない。しかし、このたび正法を求める願いはきっと叶えられると期待していた。師母も灌頂を認めてくれると思っていたのではないのか。彼は、天から地に撃ち落されたように辛かった。
彼は自分の部屋に戻っても、身がよじれるようで一晩中まんじりともせず、絶望感が波のように押し寄せてきた。「もし正法を得られなかったら、この世に生きていても何の意義があろうか?」
あくる日の早朝、師父はウェンシーのところに来て言った。「怪力君、あの十層建ての建築の方はしばらくの間ほうっておいていい。今度はお客さんを泊める城楼を築いてほしいのじゃ。柱は十二柱で、その隣には大きめの修定室があるものじゃ。うまくできたら、法を伝えよう」
こうしてウェンシーは堡塁の方はしばらく放っておいて、城楼を建て始めた。
光陰は矢の如し、ウェンシーは自身の背中と腰の傷を忘れて、仕事に没頭した。ついに、この大きな城楼は順調に完成しつつあった。
(続く)
(翻訳編集・武蔵)

















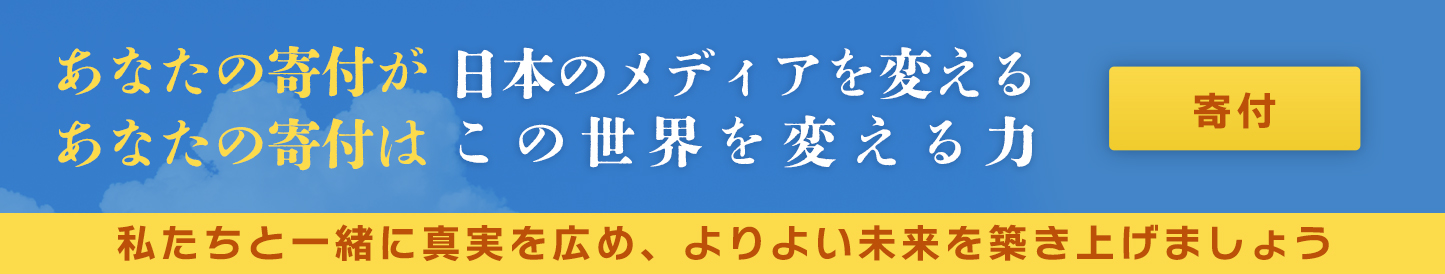
 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。