4月29日の「昭和の日」東京で開催された「財務省・厚労省解体」を訴える大規模なデモ集会には、数千人の市民が集まった。デモの趣旨にはさまざまな不満が込められていたが、注目を集めた一つに薬害問題に関する発言があった。
この日、登壇したのは、1990年代の薬害エイズ訴訟の原告の一人であり、後に参議院議員となった川田龍平氏だ。川田氏は「薬害をなくしたいという思いで活動してきた」と語り、現在の新型コロナウイルスワクチンの問題に対し、「もしこれが薬害でなければ、何が薬害なのか」と強い疑問を投げかけた。
薬害とは、本来病気を治すはずの薬が原因で、健康被害をもたらすことを指す。日本ではこれまで、薬害スモン(1960年代)、薬害エイズ(1980~90年代)、薬害C型肝炎(2000年代)など、重大な事例が繰り返されてきた。共通する問題として、被害の発覚が遅れたことや、厚生労働省や製薬企業による情報公開の遅れ、責任の所在が不明確だったことなどが挙げられている。
川田氏の発言は、こうした歴史が今も教訓として生かされていないのではないか、という懸念に基づいている。実際に、新型コロナウイルスのワクチン接種に関しては、副反応の報告や因果関係の評価方法について、一部の専門家や市民団体から不透明だという声も上がっている。
厚生労働省は、新型コロナワクチンに関して「接種による利益が副反応などのリスクを上回る」とする立場を維持しており、2021年以降、緊急使用承認の形で複数のワクチンが短期間に接種された。その一方で死亡事例や重篤な副反応の報告もされている。
新型コロナワクチン接種後に健康被害が生じた後、予防接種健康被害救済制度で認定された人数は接種開始後4年余りで994件(2025年3月18公表分まで)となり、制度開始後48年間ですべてのワクチンで認定した159件(2025年3月18公表分まで)を遥かに上回っている。
ワクチンの有効性については議論は分かれている。The Lancet誌では「初期段階では有効だったが、変異株には効果が限定的」とする研究発表が出ている。
厚生労働省は、接種後の健康被害については、現時点でワクチンとの明確な因果関係は確認されていないとする立場を維持している。一方で、専門家や一部の市民からは、その評価手法や情報公開のあり方について疑問の声も出ている。川田氏も「予防原則に基づいた慎重な対応がなされなかったことが被害の拡大につながった」と指摘する。
予防原則(Precautionary Principle)とは、化学物質や遺伝子組換え技術などの新技術が、人の健康や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす恐れがある場合、たとえその因果関係が科学的に十分証明されていなくても、被害を未然に防ぐために規制措置や対策を講じるという考え方で、1980年代から欧米を中心に環境政策や化学物質規制の分野で導入されてきた。
なぜ薬害は繰り返されるのか。その背景には、国の医薬品行政のあり方、企業と行政の関係、そして市民への情報提供のあり方が関係している。薬害エイズ訴訟では、当時の厚生省(現在の厚生労働省)と血液製剤メーカーが、危険性を認識しながら非加熱製剤の販売を続けていたとされる。この事件を受けて、医薬品の安全性評価や情報公開体制の強化が求められたが、現場では依然として「形式的な審査」や「利害関係のある専門家による検討委員会」などが批判の的になっている。
一方で、製薬業界にとっては、新薬の迅速な開発と承認が国際競争の中で不可欠であり、安全性とスピードのバランスが常に問われている。行政はその中で、国民の健康を守る立場としてどこまで透明性を保てるかが、今後の信頼回復の鍵となる。
薬害の問題は、単に過去の過ちとして片づけることはできない。なぜなら、それは制度や文化の中に深く根付いた問題であり、根本的な改革なしには再発を防ぐことは難しいからである。特にワクチンは病気を抱える者ではなく健康な者に接種するものであり、健康被害や死亡者が出ることは許されない。
川田氏は「薬害を繰り返さないためには、検証と反省が不可欠だ」と述べた。薬害の教訓を生かすために、国や行政、企業、市民社会がどう行動するかが今、問われているだろう。










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




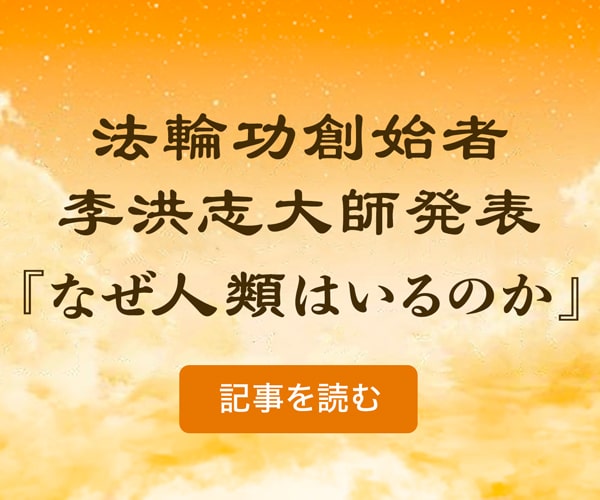
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。