政治亡命を試みる中国領事館職員の董さんは秘密のルートでSIMカードを入手し、脱出ルートも確保した。あとはチャンスを待つだけだったが、それは思いもよらない形で訪れた。
(上)をまだお読みでない方はこちらから。
災い転じて福となる
2018年5月6日は日曜日だった。董さんは昼間から教会に向かったが、領事館に帰ると上司の黄氏から複数の不在着信が残っていた。上司は董さんを呼び出すと終始険しい表情で叱責したが、教会への訪問については特別触れなかった。
翌日、勤務以来ずっと領事館で管理されていたパスポートが一時的に職員の元に戻ってきた。新たに配属された者は自動車協会でニュージーランドの免許証に切り替える必要があったからだ。
切り替え手続きが終わると、上司は董さんをオフィスに呼び出し、「紀律違反処分通知書」にサインするよう命じた。「今回は中程度の規律違反で、まだ重度ではない。重度の規律違反であれば、サインするまでもなく、そのまま帰国だ」。
部屋で上司の叱責を受けていると、係員が言付けのために入ってきた。海外から高官らが到着するため、空港に出向き歓迎するようにとのここだ。上司は何も言わずに席を立ち、董さんのパスポートを回収しないまま部屋を後にした。
董さんはパスポートに目を落とした。「千載一遇のチャンスだ」と思い、脱出を決心した。
董さんは当時のことを振り返る。「まだ真昼間だった。今でも思い出すと当時の緊張が蘇る。私はすぐに部屋に帰って荷物を片付け、カバンに詰め込んだ。そして周りの様子を伺った」。
「通常であれば同僚が休憩に帰ってくる時間だ。彼らに今どこかと聞けば、空港に向かっている最中との返事が返ってきた。フロアには誰もいなかった。監視の目もない。荷物をまとめると、時計は12時半を指していた」。
「我々一般職員は11時半に食事を取り、総領事の許爾文氏はいつも12時頃に食事をしていた。12時半には食べ終わるだろう。他のスタッフは休憩に入っていた。新しい物件の門は内側から開けられる。道路を渡ればいつもの教会だ。地理勘はあった」。
董さんがまさに最初の一歩を踏み出そうとしたとき、一抹の不安が頭をよぎった。「躊躇していると、突然『行け、行け』という声が聞こえてきた。思わず振り向いたら誰もいなかった。これは神様のお導きに違いないと思い、ためらいを打ち消した」。
董さんが宿舎を出る時、玄関にはわざと予備の靴を置いておいた。
「私は帽子を深くかぶり、大小二つのキャリーケースを持って走った。すぐに道路を渡った。右手には大きいケース、左手には小さいケース。あまり多くのものを詰め込まず、仕事用の服装も置いてきた。できるだけ身軽にしたかった」。

「領事館から教会まで、早歩きで3分ほどの距離だ。昼になると、多くの人が領事館の周りのオフィスビルから出てきて、タバコを吸い歓談していたが、その日に限っては誰もいなかった。心臓の鼓動が聞こえるほど、あたりは静まりかえっていた」。
重なる不運
董さんは足早に教会に向かった。何度も訪れた場所だが、今日とばかりに鍵がかかっていた。運悪くインド人の神父も不在だった。董さんは唖然とした。またしても想定外のことだ。領事館の外で知っているのはインド人の神父だけなのに。
教会の玄関に荷物を置き、周りを見渡すと、近くの教会学校で女性教師が子供たちに授業しているのが目に入った。董さんは流暢とは言えない英語で話しかけた。神父に助けを求めたい、代わりに連絡を取ってもらえないか、と頼み込んだ。
「完全に行き当たりばったりな状態だった。弦を放たれた矢のように、後戻りなどできなかった」。
翻訳ソフトを介した短いやり取りだった。女教師も神父を探したが、いまだ連絡は取れないまま。女教師は彼の緊張した素振りを見て、董さんを自分のオフィスに案内し、座って休憩を取らせた。時間だけが刻一刻と過ぎて行く。董さんのスマートフォンは料金不足で電話をかけられなくなった。
数分後、パトカーのサイレンの音が近づくのが聞こえた。女性教師が警察に通報したのだ。「もはやこれまでか。拘束されたら領事館に引き渡されるだろう」と董さんは考えた。
オフィスのドアが開き、二人の警官が入ってきた。右手で拳銃のホルスターを押さえ、腰を落とし、左手で「動くな」とジェスチャーをした。
焦るなか、董さんは首に掛けていた十字架のネックレスを思い出し、警官に見せた。女性教師は何かを悟ったようで、警官に近づいて話をすると、警官の態度はすぐに和らいだ。
董さんはありのままを話した。「私は中国領事館から逃げ出してきた。もし領事館に送り返されたら命はないかもしれない。領事館以外の場所ならどこに連れて行っても文句はない」。
警官は事情を呑んでくれたのか、「心配するな」と言い、董さんを警察署に移送した。
奇跡の連携プレー
董さんは警察署に着くと、以前オンライン上で連絡をとっていたオーストラリアの民主活動家と連絡を取った。民主活動家はさらに知り合いのニュージーランド人に連絡を取り、そのニュージーランド人もまた自身の知り合いに連絡をとった。このような「リレー」は続き、最終的に6人目の「ランナー」が警察署にやってきて、董さんを弁護士事務所まで送り届けた。まさに奇跡の積み重ねだと感じた。
一連の脱出劇について、董さんは「無謀だったが、我ながら良い決断だった」と振り返る。「パスポートがあまりにも入手困難だった。一度手元から離れると、二度とチャンスは来ないかもしれないと思った」。
董さんがのちに中国領事館の元職員から聞いたことだが、自室の前に置かれた靴が時間稼ぎとなり、脱出が発覚したのは24時間後だった。他の領事館員は当初、上司に怒られた董さんが引きこもっていると勘違いしたという。
董さんの亡命から半年、ニュージーランド政府はその政治亡命を正式に認めた。董さんはアルバイトで生活を繋ぎ、脱出時に中国領事館から借りた600ドルも数年後に「返済」したという。
国に残してきた家族は中国共産党の様々な部門から嫌がらせを受けた。董さんの妻は夫の亡命を知った後も想いを変えず、女手ひとつで子供を養った。数年の長い月日を経て、一家はやっと再会を果たすことができた。
(了)









 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram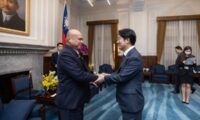





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。