2025年春、日本の米市場では価格高騰と品薄が深刻化し、政府は備蓄米の市場放出を決定した。しかし、農林水産省(農水省)の対応は遅く、消費者の視点を欠いた姿勢が目立ち、厳しい批判が集中した。備蓄米の放出決定から1か月半が経過しても、消費現場に届いた米の量はごくわずかであり、米価高騰や消費者不安に対する対応として不十分な状況が続いている。
具体的に言えば、JA全農が落札した備蓄米約19万9千トンのうち、2025年5月1日時点で卸売業者への出荷は29%(約5万7千トン)にとどまっている。さらに、4月13日時点で小売業者や外食産業に届いたのは、放出量のわずか1.97%であった。流通の遅れには、精米、袋詰め、事務処理といった工程の時間的制約や、流通業者の準備不足が関係している。
こうした事態にもかかわらず、農水省は迅速な対策を取らなかった。この対応は、消費者の立場を軽視し、米価高騰を黙認する態度と捉えられる。農水省は、政権側の指示を受けた後に動き出した点や、放出後の流通管理に不備があった点も問題として浮上した。
農水省の対応策
農水省は2025年5月2日、JA全農に対して備蓄米の迅速な供給を強く求めた。この要請は、放出後も進まない流通状況に対処するものであり、卸売業者への出荷加速を意図している。
従来、備蓄米の放出には「流通不足時」などの条件が必要であったが、農水省は運用指針を見直し、流通の停滞時にも市場への迅速な放出を可能とした。これにより、需給逼迫や価格高騰への機動的な対応が現実的となっている。
政府は2025年2月時点で21万トンの備蓄米を市場に放出する方針を決め、3月中旬より引き渡しを開始した。入札方式により売渡先を決定し、応札価格の高騰や特定業者による買い占めを防ぐ目的で、集荷実績に基づいた上限を設定した。売渡先には隔週で販売数量や金額などの状況を農水省に報告させ、同省がそれらを集約・公表することで、流通状況の可視化と管理を強化している。
今後も農水省は、需給状況や市場価格の変動を注視し、必要に応じて21万トンを超える追加放出を検討している。また、精米や袋詰め、事務処理といったボトルネックの解消に向けて、JA全農や卸売業者に対し作業の迅速化と効率化を求めている。加えて、小売業者や外食産業への供給ルートの強化にも力を入れている。
消費者の不満
米の取引価格は前年同期の2倍以上となり、店頭価格も過去最高を更新した。政府の備蓄米放出によっても価格はほとんど下がらず、消費者の不満が高まっている。
備蓄米の放出決定後も、スーパーや小売店でその姿を見かける機会は少なく、「備蓄米はどこにあるのか」との疑問が広がっている。2025年4月時点では、放出された備蓄米のうち消費現場に届いた割合は2%未満という報道もあり、流通の停滞が顕著である。
備蓄米の多くは、大手コンビニ、量販店、外食企業に優先的に供給され、中小スーパーや米穀小売店には十分な供給が行われていない。玄米での仕入れが禁止されていたため、米穀小売店は備蓄米を扱うことができず、農水省への批判が一段と強まった。
農水省の対応は遅れ、消費者の生活実感や不安に寄り添う姿勢が見られなかった。生産者や業界団体の意向を優先し、消費者の立場を軽視した姿勢が指摘されている。農水大臣は「味に問題はない」と主張するものの、多くの消費者は「早く安く手に入ること」を求めており、政府の説明と現場の実情との乖離が浮き彫りとなった。
その結果、日本米に代わってベトナム産ジャポニカ米などの外国産米を購入する消費者が増加し、「安価な米を求めて輸入品に流れる」現象が起きている。






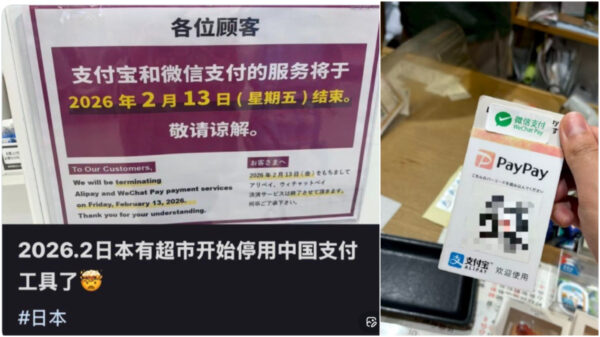


 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram



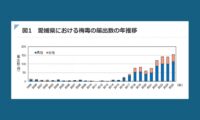

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。