流通大手のイオンは5月13日、米国・カリフォルニア産のカルローズ米を100%使用した新商品「かろやか」を発売すると発表した。6月6日から、都市部の店舗を中心に順次展開。コメの価格高騰や品薄感に対応する。
2024年夏以降、日本の米市場はかつてない混乱に見舞われている。猛暑や台風による不作、円安・資材高騰など複合的な要因が重なり、2025年春を迎えてもなお、国産米の高騰と品薄状態が続く。家計を直撃するこの「令和の米騒動」の出口は見えず、消費者の不安が広がる中、店頭ではカリフォルニア米や台湾米といった外国産米の流通が急速に拡大している。現場の実態と今後の展望を、輸入米の動向を中心に追った。
止まらぬ国産米の高騰――家計に重い負担
2025年3月時点で、東京都区部のうるち米(コシヒカリ以外)の5kg小売価格は4239円と、わずか1年で2倍近くに跳ね上がった。総務省の消費者物価指数でも、米類は前年同月比+70.9%と主食群で突出した上昇を示している。卸売市場のスポット取引では、関東銘柄米の1俵あたり価格が前年の3倍近くに達し、家庭の年間負担増は2万円を超える計算だ。こうした高騰の背景には、2023〜24年の異常気象による収穫量減少、コロナ禍明けの需要回復、資材・肥料・人件費の上昇などが複雑に絡み合っている。
備蓄米放出も効果限定的 制度の壁と流通停滞
政府は価格抑制策として、2025年1月以降に備蓄米の市場放出を進めてきた。だが、その効果は限定的だ。備蓄米は「需給安定法」に基づき、年間5千トン以上の仕入実績を持つ大手集荷業者しか入札に参加できない。実際、2回目までの放出分の94%をJA全農が落札したが、5月1日時点で出荷されたのはわずか29%。市場に出回ったのは全体の1.4%にとどまり、消費者の手元にはほとんど届いていない。
入札方式は市場原理を反映しやすい一方、需給逼迫下では高値落札が常態化し、小売価格の抑制効果は薄い。また、転売防止策や大手業者への集中が流通停滞を招き、中小卸や小売店への供給が滞るという構造的な問題も浮き彫りとなった。政府は4月から業者間販売を認めるなど制度の見直しを進めているが、依然として「備蓄米はどこに?」という消費者の声は絶えない。
急増する輸入米――カリフォルニア米・台湾米が食卓に
国産米の高値と品薄を背景に、外国産米の流通がかつてない勢いで拡大している。農林水産省によれば、2025年2月の民間企業による米輸入量は523トンと、2024年度の年間輸入量(368トン)を1か月で上回った。2024年4月〜2025年2月の10か月間では991トンと、前年度比2.6倍以上に達した。民間輸入には1kgあたり341円という高関税が課されるが、それでも国産米より割安な場合が多く、外食産業やスーパーが積極的に輸入を拡大している。

カリフォルニア米――「カルローズ」旋風
アメリカ・カリフォルニア州産の「カルローズ米」は、さっぱりとした食感と粘りの少なさが特徴の中粒種。2025年6月からはイオンが4kg2680円(税抜)で新商品「かろやか」を全国販売するなど、流通大手が続々と取り扱いを開始。カリフォルニア米はもともと日本食レストランや加工用に「ミニマムアクセス米」として政府輸入されてきたが、近年は民間貿易による主食用の輸入も急増。2024年には民間輸入申請が過去最大となり、スーパーや外食チェーンでの存在感が急速に高まっている。
消費者の評判も上々で、「日本米と大差ない」「チャーハンやリゾットに合う」といった声が目立つ一方、「粘りが少なく和食やおにぎりには物足りない」との指摘もある。価格や安全性を重視する層からは「産地偽装がないので安心」といった支持も広がっている。
台湾米――品質と安全性で存在感
台湾産米もまた、日本のスーパーでの取扱いが拡大。2024年11月からは西友が関東138店舗で「むすびの郷」を販売開始し、台湾の高品質米「台南11号」などが日本市場に投入されている。台湾米は日本と同じジャポニカ種で、もちもち感やふっくらした食感が特徴。炊き方を工夫すれば日本米に近い食味が得られるとの評価もあるが、「冷めるとややパサつく」といった声もある。安全性面では600項目以上の残留農薬検査をクリアし、消費者の安心感につながっている。
価格は1kg750円程度と、国産米(1kg900円前後)と大きな差はないが、安定供給と品質のバランスで選ぶ消費者が増えている。
輸入米拡大の背景と影響――選択肢の多様化と国産米への課題
外国産米の流通拡大は、短期的には価格高騰の緩和や品薄解消に寄与している。特に外食産業や加工用米市場では、コスト削減のために輸入米の使用が急速に広がる。一方で、国産米市場や日本の農家への影響も懸念される。消費者が輸入米に慣れれば、将来的に定着する可能性もあるが、日本のブランド米やプレミアム米へのこだわりは根強く、今後は「用途や価格で使い分ける」消費スタイルが主流となりそうだ。
農林水産省や業界団体は、国産米の品質向上やブランド化、輸入米とのすみ分けを模索しているが、米農家の高齢化や担い手不足、生産基盤の脆弱化といった構造的課題は依然として深刻だ。
今後の展望――「米騒動」収束は見通せず
現時点で、国産米の高騰と品薄が「完全に解消する時期」は見通せない。専門家は、2025年秋の新米収穫が順調であれば、2026年春ごろから価格が落ち着く可能性を指摘するが、異常気象や災害が続けば再び不作や高騰のリスクも残る。備蓄米放出や輸入米拡大は一時的な緩和策に過ぎず、根本的な需給安定には増産支援や新規就農者の確保、所得補償など抜本的な政策転換が不可欠だ。
消費者にとっては、今後も価格動向に注意しつつ、カリフォルニア米や台湾米など多様な選択肢を活用することが現実的な対応策となる。日本の食卓は今、国産米と輸入米の「共存時代」に入りつつある。






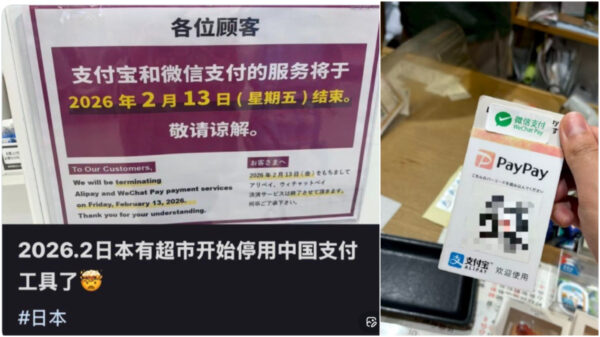


 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram



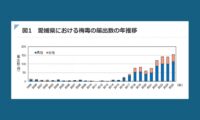
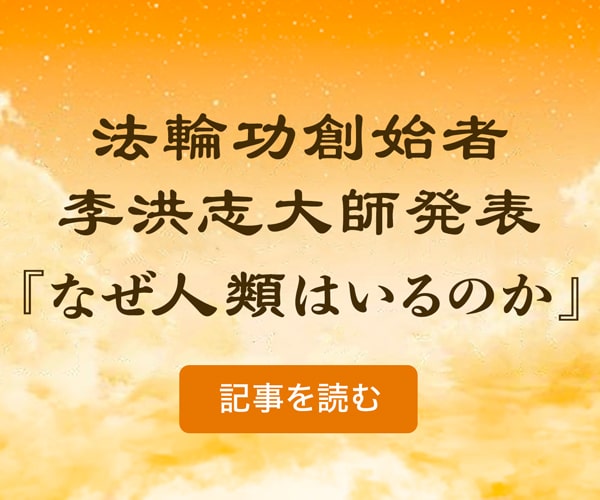
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。