この3か月、私はデンマークで生活してきた。本当に大好きだ。街は清潔で、自転車専用レーンは隅々まで整備されており、人々の間には公共への深い信頼が根づき、その空気はアメリカ出身の私にとっては驚きであり、心地よいものだった。 医療は「無料」、大学には奨学金制度があり、多くの市民が「政府は機能している」と感じ——こうした側面から、この国が理想化されるのも無理はなかい。
だが、滞在期間が長くなるにつれて、表面からは見えにくい「綻び」が徐々に目につくようになった。それは、ただの会話の流れや、海外の友人たちの何気ない話の中、あるいはふとした瞬間に感じる微かな違和感として現れた。 多様性や個人主義が社会の根幹にあるアメリカで育った私は、デンマークでの暮らしに安心感をもたらしているこの社会の仕組みが、何かを犠牲にして成り立っているように思えた。
ゲットー法 制度化された「線引き」
2018年、デンマークは「ゲットー計画(Ghettoplanen)」として知られる法律を導入し、その後「並行社会法(Parallel Society Laws)」と改称した。これらの政策は、住民の過半数が「非西洋系」とされる地域を対象としていた。
「非西洋系」とは、EUおよび北アメリカ以外の国に出自を持つ人々が含まれ、生まれがデンマークであっても、また市民権を持つ第2世代・第3世代であっても該当する。たとえば、祖父母がトルコ、レバノン、ソマリアなどから移住してきた子供も、法律上「非西洋系」に分類された。
こうした地域が一定の基準──低所得、高失業率、住民の多数が「非西洋系」であること──を満たすと、政府による介入の対象となる。その主な内容は以下の通り
「デンマーク的価値観」を教えるため、1歳からの就学前教育を「非西洋系」の子供に義務付け
- 対象地域での犯罪に対して、他地域よりも厳しい刑罰を適用
- 公営住宅の取り壊しと、住民の強制的な移住によって、移民人口の過度な集中を是正
- その地域への移住者を制限し、「非西洋系」住民の数に事実上の上限を設けている。
政府はこれらの施策を「社会統合のため」と説明しているが、実際には、人口構成を操作する政策に近く、そこには、「ある地域に文化的な違いが多すぎるのは望ましくない」という、明確なメッセージが透けて見える。
アメリカとの既視感──過去の政策ではなく、現在の法律として
アメリカ出身の私にとっては、どこか不気味なほど見覚えのある光景だ。標的にされた住宅政策、「好ましくない地域」といった曖昧な表現、そして国家の力によってコミュニティを作り変えようとする姿勢……。これらはすべて、アメリカでかつて行われていたレッドライニング(人種や階層による住宅差別)を思い起こさせた。 違いがあるとすれば、それがアメリカでは歴史的な「負の遺産」とされているのに対し、デンマークでは今なお現行法として存在し、国の政策として、文化的同質性の維持を目指している点だ。
表向きは「社会の一体性」という正当な理由づけがなされているが、実際には人々がその祖先の出身国によって選別され、生活の選択肢を制限されていた。この仕組みが、どれほど静かに、しかし確実に“排除”を進めているか。そのことを、現地での暮らしを通じて、実感せざるを得なかった。
「違い」が不利になるとき デンマークが抱える静かな排除の構造
デンマークのような福祉国家は、税金によって成り立っているだけではない。その根底には、共有された文化的土台がある。社会契約の前提となるのは、「私たちは同じように暮らしている」という共通理解だ。価値観、行動様式、生活スタイルにおいて、一定の一体感があること。それが信頼と連帯を生む要因でもある。こうした基盤は、人々の間に信頼や連帯感を生み出す一方で、排他への力も生み出す。
言語、宗教、服装、世界観といった「目に見える違い」は、こうした均質性を揺るがす存在として受け取られがちだ。そして、デンマーク社会がその違いに直面したとき──多様性を受け入れるのではなく、政策や社会的な規範によって「同化」を促す傾向があった。
つまり、それは「統合を歓迎する姿勢」ではなく、要求なのだ。その結果、完全に同化できない、あるいは同化を望まない人々は、目立たぬ形で排除されていく。
あるネパール出身のネイルアーティストは、何年もデンマークに住んでいるにもかかわらず、地元の友人がほとんどできないと語った。私の南アジア系や中東系の友人たちもしばしば、ナイトクラブの入口で「満員です」といった曖昧な理由で入場を断られるが、一方で、白人のデンマーク人たちは何事もなく入場できる。
こうした体験は決して稀ではない。EU基本人権庁の調査によれば、デンマークに住む移民は、EU平均よりも高い割合で差別を経験しているという。福祉制度や制度的信頼では世界のトップに位置するこの国だが、「多文化共生」に関しては、むしろ最低ランクに近い評価を受けていた。
「見えない差別」が生み出す静かな壁
こうした排除の多くは、目に見えにくい。明文化された法律や扇動的な言説によってではなく、日常のやり取りや住宅政策、そして暗黙の期待を通して静かに行われていた。差別は構造的で、巧妙で、そしてしばしば自覚すらされていない。その「静けさ」こそが、問題を可視化しにくくしている要因だった。
この「同調圧力」の核心にあるのが「ヤンテの掟(Janteloven)」という考え方だ。これは「目立たないこと」「自己主張しないこと」を美徳とする北欧独特の社会規範である。表面的には、謙虚さを重んじる文化として機能するが、それは同時に、文化的・個人的な違いを、目立たせないようにする力としても作用する。
多くのデンマーク人にとっては一体感を生み出すが、外から来た人にとっては「見えない壁」にもなった。さらに、国が一体性を奨励する政策を、制度として持ち合わせていることで、この文化規範は単なる習慣を超え、社会の「同質性維持装置」として機能する。
対照的に、アメリカ社会は、多くの問題を抱えながらも、個人主義を重んじる文化を土台とし、文化的な違いは常に円滑に受け入れられるわけではないが、それでも「違い」は国家の構成要素として認識されており、脅威ではなく多様性として捉えられることが多い。
統合は、中央政府が定義する「あるべき姿」に従うことではなく、学校、職場、地域社会といった現場での自発的な関わりの中で進んでいく。もちろんそのプロセスは複雑で混沌としているが、それゆえに人々は、自らのやり方で「所属」を築く余地がある──同調ではなく、「自由」を通じて。
デンマークが投げかける静かな警鐘
私はデンマークに来たとき、「よく設計された福祉国家」としての魅力を肌で感じることを期待していた。そして多くの点において、それは事実だった。デンマークは効率的で、安全で、主流の枠組みにうまく収まる人々にとっては、非常に快適な場所だ。
しかし同時に、この制度がいかにして「違い」を「混乱」と見なし、排他的で硬直的なものになり得るのかを、目の当たりにした。 安心を支える制度が、柔軟性を失い、「異なること」を受け入れない硬直した社会構造に変わってしまう──その危うさを実感した。
この経験から得た教訓は、明確である。包括の条件として「同じであること」を求める社会は、何か大切なものを失っているのではないか。
真の平等とは、上から押しつける社会設計ではなく、人々が異なる生き方をし、それでも共に暮らせる自由のなかから育まれるものだ。
多様な価値観が交わり、自由に意見を交換し、文化や信条の違いがあっても排除されない──そんな社会こそが、持続可能な共生を実現する土壌となるのではないだろうか。








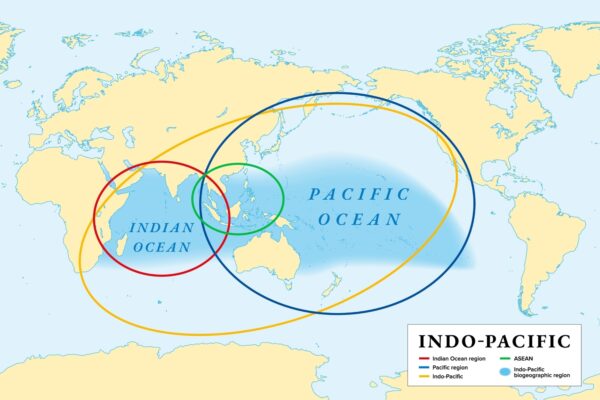

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。