今日の世界は、経済が動揺し、倫理が崩壊し、価値観が歪んでいる。指導者は不安に駆られ、企業家は途方に暮れ、一般の人々も心に焦燥と恐怖を抱えている。
確かに、技術は進歩し、物質は豊かになったが、人の心は欲望の罠に落ち込んだかのようだ。誰もが効率、利益、支配、達成を追い求め、自己中心的で冷淡になり、競争と不安に満ち、片時も安らぎがない。
迷いの中で人々は目覚め始めている。これは自滅への道だ。乱世の中、人々は古の教えを思い出し、道徳の復興を渇望している。上に立つ者には、先人たちのように「自分のためでなく、民のために尽くす」覚悟が求められ、国家や企業を困難から導き出すことが望まれている。
そこで、今日は孔子が最も敬愛した周文王から話を始める。古の教えを取り戻し、希望を見出そう。
一、周文王 姜子牙を恭しく迎える 車を八百歩推し、八百年の天下を得る
西周初年、商王朝は腐敗し、天命は移ろうとしていた。周文王は広い視野と深い仁心を持っていた。彼は、七十を過ぎて学識豊かな賢者・姜尚(姜子牙)が渭水のほとりに隠棲していると聞き、みずから訪ねた。
姜子牙は水辺で釣りをしていたが、餌を使わず、釣り針をまっすぐにしていた。彼が釣ろうとしていたのは魚ではなく、人の心であった。彼は文王を試していた。文王はそれを見て王者として振る舞わず、車を降りて歩き、恭しく出山を請い、自らの車に姜子牙を乗せ、自分は車夫となって八百歩車を押した。その誠意は姜子牙を、そして天地をも感動させた。
文王は姜尚に言った。「私は自分のためにあなたを請うのではない。天下の民のためだ」
この誠意によって姜子牙は出山し、周を助けて天下を定めることとなった。文王の死後、息子の周武王がその志を継ぎ、姜子牙の補佐のもと商を滅ぼし周を建てた。これが周が八百年の天下を得た由来である。天は常に徳ある者を選ぶ。
二、周文王 枯骨にまで恩沢を及ぼし、諸侯を服従させる
周文王がこれほどまでに賢者を求めることができたのは、日頃からの修養によるものである。彼がまだ商の西伯侯であった時から、非凡な仁徳と見識を示していた。
あるとき、巡察中に野に埋葬されていない枯骨を見つけ、随行の官吏に丁重に埋葬させた。官吏は「これは無主の骨であり、気にする必要はありません」と言ったが、文王は「天下を治める者は天下の主、一国を治める者はその国の主である。これらの枯骨が私の領地にある以上、私は彼らの主である。どうして彼らを野に晒したままにできようか」と言い、衣棺で改めて埋葬させた。
このことを知った人々は「西伯の恩沢は無主の枯骨にまで及ぶ。まして生きている者にはなおさらだ」と称賛した。
現代の人は人性を疑い、これを名声目当てだと思うかもしれないが、人の見識は装うことができない。文王の仁徳は、諸侯の争いに対する姿勢にも表れている。公明正大であったため、諸侯は彼に難題の裁決を求めてきた。
あるとき、虞と芮の二国が田地をめぐって争い、周に裁決を求めてやってきた。だが、周の地に入ると、民が互いに譲り合い、礼儀正しく暮らしているのを見て、自らの争いが恥ずかしくなり、和解して裁決を求めることをやめた。この出来事は、文王の徳による感化の力を示すものである。民がこれほどまでに徳を持つのは、文王の教化の賜物であり、まさに臣民の模範であった。だからこそ諸侯は自ら帰服し、天下の心を得たのである。
文王の仁政と徳行は、民を感化しただけでなく、後世に治国の範を示した。天下のために頭を垂れ、賢者のために腰を折り、無主の遺骨を憐れみ、諸侯の争いを裁く君主は、自然と人心と天の助けを得るのである。
三、周公吐哺 文王の遺風を継ぎ、天下を安定させる
周公と周武王はともに周文王の子である。武王は即位後、商を滅ぼしたが早世し、子の成王は幼少であったため、周公旦が摂政を務めた。当時、天下は未だ安定せず、諸侯は周公が王位を奪うのではと疑った。周公は弁解せず、実際の行動で忠誠を示した。
彼は昼夜政務に励み、『史記』によれば「賓至れば未だ嘗て吐哺握髪してこれを迎えざることなし」とある。つまり、賢才が来れば食事中でも咀嚼をやめ、髪を結ぶ暇もなく迎えに出たという意味であり、賢才をもてなすことに細心の注意を払っていたことを示している。これは文王の遺風を受け継ぎ、賢者を礼遇し、身を低くして国を治め民を安んずる徳政をさらに深く根付かせ、後世に伝えたものである。
周公は六年間、心を尽くして政務に励み、ついに天下を安定させた。成王が成長した後は、権力に執着することなく、政権を完全に返還した。
孔子は周公を非常に尊敬し、「我、仁を欲すれば、すなわち仁至る」と述べている。孔子が説いた「礼」は、周公が築いた「周礼」であり、仁徳によって国を治める制度と精神、すなわち無私・克己・勤政・敬才・愛民を体現したものである。これが後世の帝王たちの治国の模範となった。
四、劉備の三顧の礼「力が弱くても、仁徳で人心をつかむ」
東漢の末期は、多くの武将たちが争う混乱の時代だった。劉備は土地も兵もほとんど持たず、当時もっとも弱い立場の諸侯だった。しかし彼は「天下を平和にしたい」という強い思いを持っていた。
劉備は、知恵に優れた諸葛亮(孔明)こそが漢王朝を再興できると信じ、何度も自ら彼のもとを訪ねた。雪の中、山を越え、何度断られても諦めず、ついには諸葛亮の心を動かした。
諸葛亮は「劉備は私を先生や父、友人のように大事にしてくれる」と語った。劉備は部下を信じ、家族のように接し、才能ある人を心から求め、自分を低くして迎え入れた。そのため多くの優秀な人材が集まり、後世まで尊敬されている。
五、渋沢栄一 『論語』をビジネスの教科書にした実業家
明治維新後、日本は新しい国づくりが必要だった。渋沢栄一はもともと下級武士だったが、維新運動に参加し、ヨーロッパで資本主義経済を学んだ。帰国後は第一国立銀行をつくり、500社以上の企業設立をリードした。
だが彼の最大の特徴は、『論語』の教えを大切にし、毎朝朗読し、「道徳経営」を実践、利潤至上主義を否定し、商売は自分のためだけでなく、社会や国のためにするものだと考え、儒商の済世の道を実践した。
ゆえに、企業家の責任感、誠実、修身と仁愛を強調し、「商業の道もまた天下を救うことができる」と述べた。来訪者や志ある若者に対しても、周公のように身分を問わず、できる限り自ら応対し、支援を惜しまなかった。
渋沢栄一の理念は、日本の企業界に道徳と社会的責任を重んじる風土と文化を形成し、今なお深く影響を及ぼしており、世界の敬仰を集めている。
企業家も謙虚で徳があれば、国を興し民を安んずることができ、先賢や聖王の修身治国平天下の志を実践できるのである。
六、結語 「天地のために心を立て、生民のために命を立つ」古の教えを忘れるな
周文王が八百歩も車を押したこと、周公が食事中でも髪を握って急ぎ政務にあたったこと、劉備が三度も賢者を訪ねたこと、渋沢栄一が『論語』の教えで国を良くしようとしたこと――彼らに共通する精神は、敬天重徳、公正無私、謙虚仁愛である。
彼らは君主であれ重臣であれ企業家であれ、常に忘れなかった共通の使命がある。「天地のために正しい心を持ち、人々のために道を示し、過去の偉人の教えを受け継ぎ、未来の平和を切り開く」ということだ。
彼らはそれぞれのやり方で天から与えられた役割を果たし、上は天地に恥じず、下は民に恥じない生き方をした。その生き様は、後の世代にとって大きな財産となっている。
これこそが真のリーダーにふさわしい度量と姿勢である。これこそが人を迷いと困難から導く道である。
今日の世界には、才知も技術も手段も不足していない。足りないのは、天下のために頭を垂れ、民のために身を屈する仁愛の心である。
願わくは、すべての地位ある者が古人を鑑とし、名利を争わず、個人の得失にこだわらず、蒼生の心を抱き、徳ある政を行えば、乱は自ずと止み、道徳は自ずと興り、未来は自ずと明らかになる。
今日のリーダーがこれを志とすれば、天下を安んずるのみならず、歴史の栄光をも創出できる。










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




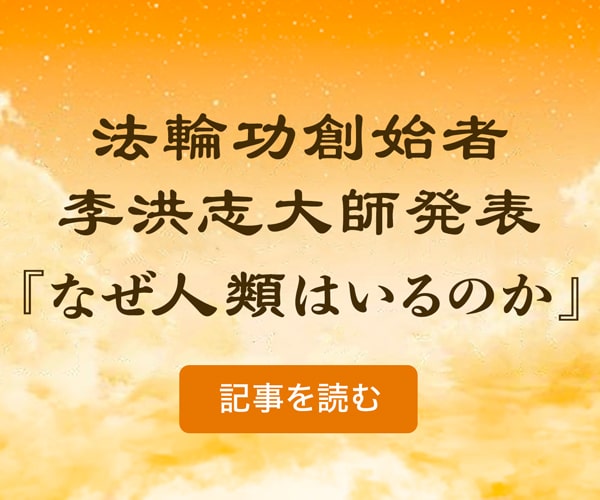
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。