5月22日、ホワイトハウスの首席経済学者は、ドルを弱めることを目的とした秘密の通貨協定が進行中であることを否定し、強いドルがアメリカにとって有益であると述べた。
同日、ホワイトハウス経済顧問委員会のスティーブン・ミラン(Stephen Miran)議長は、ブルームバーグの「Big Take DC」ポッドキャストで「アメリカは引き続き強いドル政策を維持する」と発言した。
ミラン氏は、スコット・ベッセント米財務長官が通貨政策の公式なスポークスマンであることを指摘した。「私たちはこのような(ドルを弱める)作業を秘密裏に行っているわけではない。現在、何の情報もない」と、ドルを貶値(切り下げる)させることを目的とした国際協定に関する憶測について語った。
最近数週間、トレーダーたちはアメリカの貿易相手国が自国通貨をドルに対して切り下げることに同意する可能性があると考え、貿易不均衡の問題を解決する手段として、通貨市場に変動が見られた。
トランプ大統領は、他国が意図的に自国の為替レートを引き下げて、アメリカに対して商業的な優位性を得ようとしていると批判し続けている。4月9日、トランプ大統領は対等関税の実施を90日間停止すると発表した後、アジア通貨が大幅に上昇した。新台湾ドルはそれ以来約10%上昇し、今月初めには1988年以来の最大の上昇幅を記録した。韓国ウォンも6.4%上昇した。ブルームバーグのドル現物指数はトランプ氏が就任して以来6%以上下落している。
ミラン氏は貿易交渉に直接関与していないが、「通貨政策には変化がない」と述べた。
昨年12月、トランプ大統領はミラン氏をホワイトハウスの首席経済学者に任命した。それ以前の11月、まだヘッジファンドのハドソンベイキャピタル(Hudson Bay Capital)で働いていたミラン氏は、いわゆる「マールアラーゴ協定」(Mar-a-Lago Accord)の可能な形態についての提案を含む論文を発表した。それ以来、ドルを弱体化させることを目的とした重要な合意のアイデアは、外国為替市場での議論の焦点となっていた。
ベッセント氏は、財務長官に就任した後、「強いドル政策」を強く支持し、ドルの堅調さが国にとって有利であると述べた。また、アメリカが、過去に7か国グループの声明で約束した「通貨は市場によって決定されるべきだ」という考えも支持した。
アメリカ財務省は、声明の中で、カナダのバンフで開催された7か国グループ会議の際に、財務長官と日本の財務大臣が「為替レートは市場によって決定されるべきであり、現在のドル対円の為替レートは、経済のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)を反映している」という共通の信念を再確認したと述べた。
2月6日に、ベッセント氏はブルームバーグのインタビューで、「トランプ大統領の指導の下、強いドル政策は全く変わらない」と強調した。
また「我々はドルが強くなることを望んでいる」とベッセント氏は付け加え、「他国が自国通貨を切り下げて貿易を操作することは望んでいない」と述べ、トランプ大統領もドルの世界的な主導地位を維持することを誓い、経済学者や戦略家がドルの価値を高めることができると考える政策を支持した。
ミラン議長は、ポッドキャストで、市場が彼の論文をどれほど重視したかは、政府の政策を超えていたと再確認した。また、その論文は、特定の政策を提唱することを目的としていなかったとも述べた。










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




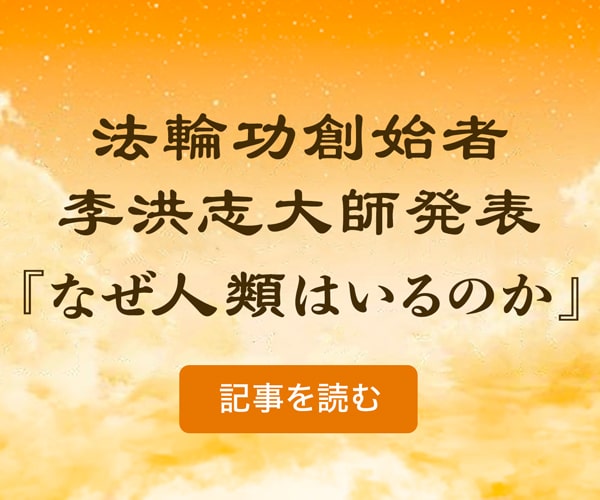
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。