中国製の太陽光パネルが、日本市場を急速に席巻している。産経新聞の調査によると、国内で2024年に出荷された太陽光パネルの約95%が海外製であり、その8割超が中国製が占めるとされる。
日本で中国製パネルが普及した背景には、価格の安さと政府の固定価格買取制度(FIT)による需要拡大がある。加えて、補助金や融資、税制優遇など中国共産党(中共)政府の手厚い支援により輸出競争力が高まり、中国メーカーは低価格で大量生産を実現した。その結果、価格競争で優位に立ち、日本市場においてもコスト重視の需要に応える形で広く普及した。
一方、日本メーカーは高品質・高価格路線を維持していたため、コスト競争で後れを取り、次第に市場シェアを失っていった。
しかしこうした中国製パネルの低価格の裏側にはこれらの政府の支援以外に深刻な人権問題が潜んでいる。2000年代前半には、日本製の太陽光パネルが世界市場で約50%のシェアを占めていたが、後半から中国製品がシェアを拡大し、2010年には日本のシェアが10%前後までに低下した。この急速な変化は、世界的な太陽光発電需要の急増と、それに対応した中国企業の大規模な生産拡大によるものだった。
経済産業省が2023年に発表した「次世代型太陽電池戦略」によると、中国は新疆ウイグル自治区を中心に、安価な労働力と電力を用いて太陽光パネルの材料であるシリコンの大量生産を行っており、コスト競争力の高いサプライチェーンを構築してきたとしている。
しかし、この「安さ」の裏側には深刻な人権問題が潜んでいる。国際労働機関(ILO)が2025年2月に発表した報告書では、中国政府が主導する形でウイグル人の強制労働が組織的に行われており、それが太陽光パネルの製造工程にも組み込まれていると指摘された。同報告書は、太陽光パネルの原材料の生産において、拘束や監視下に置かれた労働が関与している実態を明らかにしている。
アメリカはすでに2021年には「ウイグル強制労働防止法」を施行し、トリナ・ソーラーやジンコソーラーの製品について、強制労働との関連を理由に輸入を差し止めた。また、JAソーラーの関連企業も、同法に基づく制裁対象リストに加えられている。
さらに、英国シェフィールド・ハラム大学が実施した調査でも、上記3社が新疆ウイグル自治区における強制労働と深く関わっている可能性が高いと日本ウイグル協会や国際人権NGOヒューマンライツ・ナウの調査で指摘されている。
同協会がそうした強制労働調査に対して質問状を送ったが、これらの企業はいずれも明確な回答を行わず、トリナ・ソーラーとJAソーラーは沈黙を守り、ジンコソーラーは経営方針の説明にとどまった。これにより、企業として強制労働問題に向き合う姿勢が乏しいことが浮き彫りとなっている。
国際社会では、アメリカ、EU、カナダ、英国などが法的措置を講じ、強制労働を含むサプライチェーンを排除する努力を進めている。
一方で、日本では同様の対策が遅れており、中国製パネルの輸入に対しても規制はほとんど行われていない。
日本のメガソーラープロジェクトには多額の政府補助金が投入されており、最終的には国民の税金が使われている。こうした公的資金が、国際的に非難されている労働環境を支えている可能性がある以上、社会的責任が問われるのは避けられない。
日本ウイグル協会などの調査書によると、大規模メガソーラー発電所では、「トリナ・ソーラー」「JAソーラー」などの製品が上位を占めており、その出力規模は国内でも有数である。
トリナ・ソーラー製のパネルは、岡山県美作市の「作東メガソーラー発電所」で全国1位の出力を誇り、瀬戸内市の「Kirei太陽光発電所」も全国2位、同じ瀬戸内市にある「オニコウベ太陽光発電所」でも全国4位となっている。JAソーラーの製品は兵庫県三田市の「三田メガソーラー発電所」や和歌山県上富田町「和歌山メガソーラー発電所」兵庫県上郡町の「赤穂メガソーラー発電所」などで採用され、それぞれ全国5位、7位、10位の出力を記録している。
国民の多くは、再生可能エネルギーの普及を支持している。しかし、その実現手段が人権侵害に基づいているのであれば、エネルギーの「クリーンさ」は大きく損なわれる。いまこそ、日本においてもサプライチェーンの透明性を確保し、国際基準に則った調達体制を整えることが求められている。






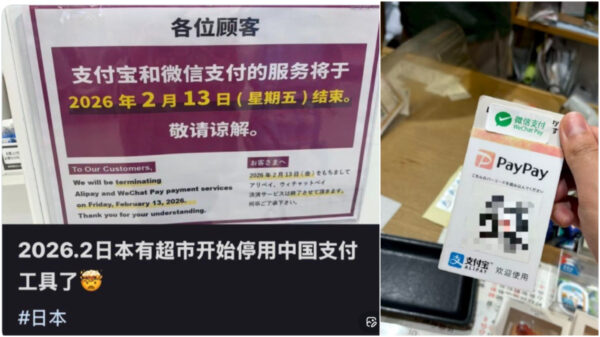



 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram



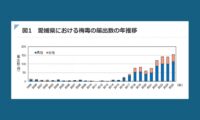
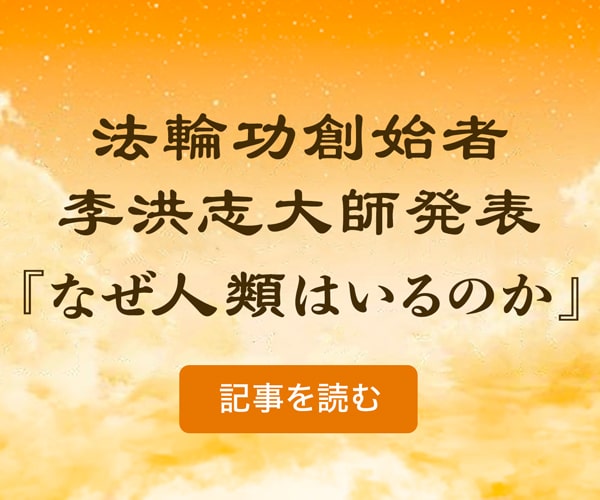
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。