5月1日、トランプ米大統領は、イランの原油および石油化学製品を購入する国や個人に対し、ただちに「二次制裁(セカンダリー・サンクション)」を科し、アメリカとのあらゆる商取引を禁止すると強く警告した。
トランプ氏は、トゥルース・ソーシャルで、「取引量の多少にかかわらず、イランの石油や石化製品を購入した者は即座に制裁の対象となり、アメリカとビジネスを行うことは一切許されない」と投稿した。
この発言は、米・イラン間で予定されていた核協議が延期された直後に行われた。4月26日に、両国は、ローマで会談を行う予定だったが、イラン側の判断で延期された。イラン高官がロイターに語ったところによると、協議の日程を再設定するかどうかは、アメリカ側の姿勢次第だという。
トランプ政権は現在、第1期政権でも実施した「最大限の圧力(Maximum Pressure)」政策を展開しており、イランの石油輸出を実質的にゼロに近づけ、核開発の抑制を狙っていて、2月以降、イランと違法に原油や石化製品の取引を行っていたとして、中国国内の中小製油所、いわゆる「ティーポット製油所」に対して制裁を発動した。
「二次制裁」とは、制裁対象国と直接関係のない第三国の企業・個人が、その国と取引を続けた場合に、アメリカ市場から排除される措置を指す。経済規模が大きいアメリカがこの制裁を行うことで、対象国への圧力は非常に大きくなると言う。
こうしたトランプ氏の対応は、中国共産党(中共)を主な対象としたものと広く見られているが、エネルギー調査会社ラピダン・エナジーのCEOで元CIA職員のスコット・モデル氏は、「現在、中共はイランから1日あたり100万バレルを超える原油を輸入している」と指摘した。
モデル氏は、CNBCの取材に対し、「ホワイトハウスが、中国の国有企業や関連インフラへの制裁を強化しなければ、現在の措置だけでは、イラン産原油の流入を止めることは難しい」と述べた。
また、今回のトランプ氏の発言について、「イランとの交渉を断念したわけではなく、むしろ“力による交渉”というアメリカの立場を明確に示したものだ」と分析した。
現在イランは、2015年に締結されたイラン核合意(JCPOA)で定められたウラン濃縮の制限を大きく超える活動を続け、トランプ氏は、イランとの新たな合意を目指すとしているが、第1期政権中にはこの合意からアメリカを離脱させた経緯がある。
この発言を受けて、同日の市場では原油価格が上昇。アメリカ産原油の先物価格は1.91%上昇し、1バレル=59.32ドルに達した。国際的な指標であるブレント原油も1.88%上昇し、62.21ドルとなった。なお、イランは、石油輸出国機構(OPEC)の主要メンバーでもあった。










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




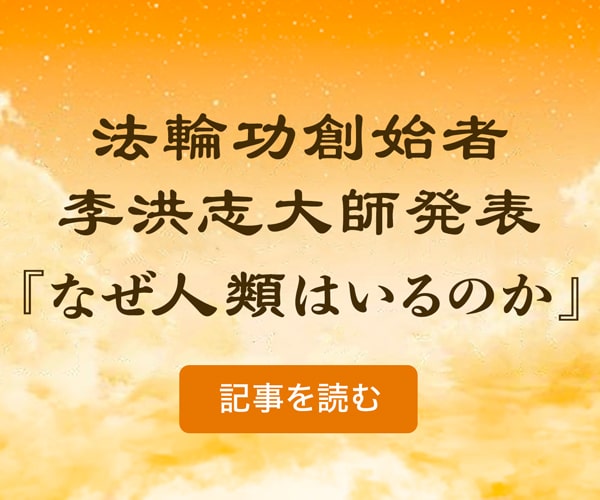
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。