2025年5月13日、東京大学の藤井輝夫総長は「本学のDEI推進について」と題したメッセージを発表した。総長は、近年一部の国々でDEI(多様性・公平性・包摂性)推進に逆風が強まっている現状を踏まえつつも、DEIの推進は現代世界が取り組むべき普遍的課題であり、日本は欧米諸国に比べて取り組みが遅れていると指摘した。その上で、東京大学も「これまで以上に襟を正して、力強くDEIの推進を行ってまいります」と宣言した。DEIは、あらゆる出自や属性の人の基本的人権を尊重する理念であり、学術の卓越性やイノベーションの源泉であると位置付けている。また、東京大学は世界の大学におけるDEI推進の取り組みに支持を表明し、ともに歩んでいく姿勢を明確にした。
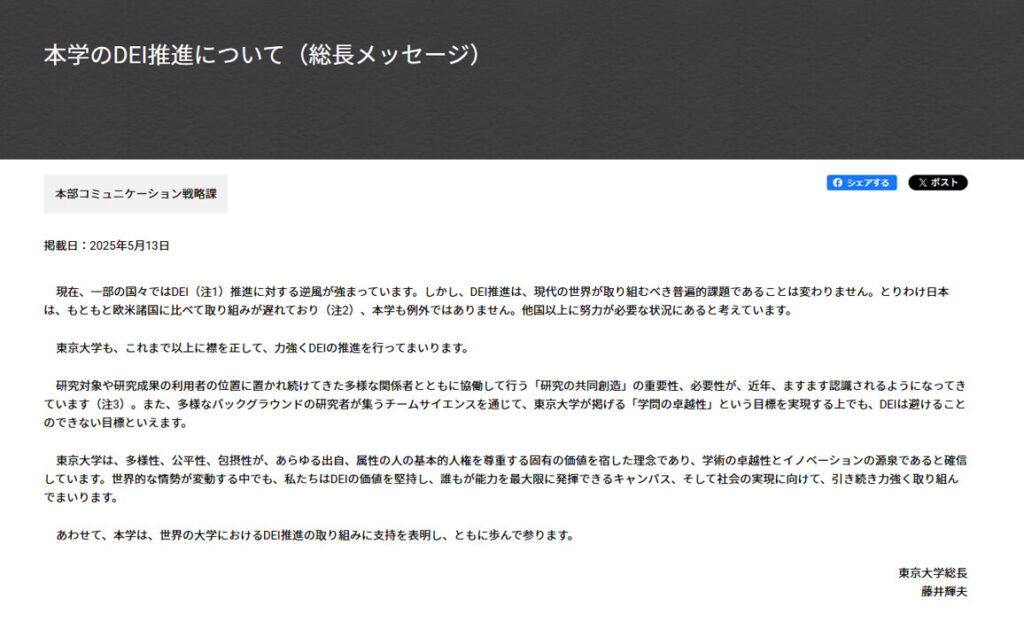
米国でのDEIの経緯と現状
米国におけるDEIの起源は1960年代の公民権運動にまで遡る。1961年にケネディ大統領が連邦政府の請負業者向けにアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)を定める大統領令を発したことが出発点である。その後、公民権法の成立や雇用機会均等委員会の設置を経て、企業や大学などで多様性、公平性、包摂性の推進が広がった。特に高等教育機関では、入学選考において人種や性別を考慮するアファーマティブ・アクションが認められてきたが、2023年6月、米連邦最高裁判所は大学の入学選考で人種を考慮することを違憲と判断した。この判決を契機に、DEI推進に対する批判や見直しが強まり、トランプ政権下では連邦政府や一部州・企業でDEIプログラムの廃止や縮小が進んでいる。一方で、DEIの意義や必要性を支持する立場も根強く、米国内では賛否が分かれる状況が続いている。
日本でDEIは必要なのか?
日本社会は歴史的・文化的に同質性が高く、欧米のような人種・宗教・歴史的差別の問題が顕在化していない。そのため、DEIの必要性については社会的な合意や強い要請があるとは言い難い。現状、DEI推進は主に女性活躍や高齢者・障がい者・外国人の活用、働き方改革など、限定的なテーマにとどまっている。少子高齢化による労働力不足やグローバル化への対応を背景に、企業や大学が国際競争力強化やイノベーション創出の観点からDEIに取り組む例が増えているが、現場では形式的な施策やパフォーマンスが先行しがちで、実質的な変化や納得感を伴う取り組みはまだ十分とは言えない。
日本においてDEIが必要かどうかは、社会や組織が直面する課題や目的によって異なる。DEIを「義務」や「モデル」として一律に推進するのではなく、各組織や個人が自らの状況や目標に応じて柔軟かつ現実的に取り組むことが重要である。社会全体としても、DEIの理念や施策が日本の文化や現実にどのように適合するかについて、今後も丁寧な議論と検証が求められる。
東京大学がDEI推進を強く表明したことをきっかけに、米国でのDEIの歴史的経緯や現状を踏まえつつ、日本社会においてDEIが本当に必要なのか、またその必要性や意義はどこにあるのかを客観的に検証し、現状と課題を整理する必要がある。東京大学の姿勢や国際的な潮流を認識しつつ、日本独自の社会的背景や現場の実感も踏まえ、DEI推進のあり方を冷静に問い直すときが来ている。






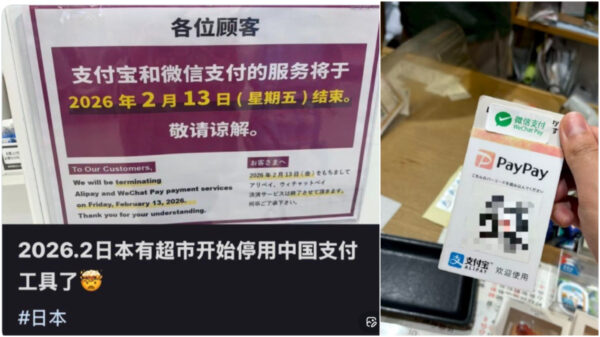


 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram



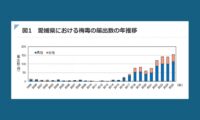

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。