北海道倶知安町(クッチャンチョウ)で、中国人が代表を務める会社が関与する建設工事をめぐり、町への届け出を行わないまま森林伐採を進めていたことが明らかになった。近隣住民の情報提供で発覚し、町は事業者に伐採届の提出を求めたが、提出は遅れ、内容にも不備があり再提出を求める事態となった。住民の証言では、当初「一部のみ伐採する」と説明していたにもかかわらず、実際には広範囲の伐採を行っていたという。
この出来事は、しばしば「中国人によるトラブル」として処理してる。しかし、その理解は問題を単純化しすぎている。なぜ彼らは同種のトラブルを引き起こすのか。
実はそれは「党文化」と呼ばれる中国共産党(中共)が民族伝統文化を破壊しながら、数十年にわたる政治運動を通じて作り上げた独自の思考様式言語体系によるものが濃厚に作用し、顕れたものだ。
どのような統治と思想の行動様式が党文化と呼ぶ思考様式を形づくってきたのか。
党文化について明確な説明をしている大紀元の社説『共産党についての九つの論評(以下、九評)』では、中国共産党が成立と支配の過程で形成したものとして邪悪な九つの遺伝子、すなわち「邪悪」「欺瞞」「煽動」「無頼」「間諜」「略奪」「闘争」「殲滅」「制御」が中国人の思考と行動の定式を縛っているとしている。
これらの遺伝子は中国共産党の施政により、中国国内で増殖し、今や中国国民の隅々にまでいきわたっており、それが海外でも中国人のトラブルの中に垣間見えている。
我が日本でも様々な場所で顕れている。倶知安の件もその一つだ。中国人のトラブルは九評が主張する「九つの遺伝子」と照合することで、別の輪郭が浮かび上がる。
たとえば、九評は「欺瞞」を次のように位置づけている。
「遺伝子その二:欺瞞—邪悪が神になりすますためには、欺瞞あるのみ」
「歴史的教訓として、共産党の承諾は信じてはならない、いかなる保証も実現しない」
ここで問題にしているのは、単なる虚偽の有無ではない。立場に応じて説明を変え、目的達成を優先し、説明責任は後回しにするという行動様式である。倶知安町の事案では「事前説明と実際の行為の乖離」「無届での工事進行」「指摘後も続いた不備」は、この様式と重なって見える。
また九評は「無頼」という遺伝子について、次のように記す。
「遺伝子その四:無頼——ルンペンプロレタリアートが中共の階級基礎を形成」
「『革命』という言葉に共産党は良いイメージを作り上げたが、実はこの『革命』は善良の人々に恐怖と災難しかもたらさず、『命』を奪うものである」
ここで言う「無頼」とは、犯罪性そのものではなく、法や秩序を内在的に尊重しない態度を指す。法は守る前提ではなく、都合に応じて回避・利用する対象となる。日本社会で当然の行政手続きの重みが共有されない場合、摩擦が生じるのは避けがたい。
さらに九評は、「略奪」についてこう述べる。
「遺伝子その六:略奪—略奪することで、新しい秩序を形成」
「中共のものはすべて、略奪してきたものである」
倶知安の森林伐採を直ちに「略奪」と断ずることはできないが、地域社会と自然環境という公共性を持つ空間が、合意や手続きを欠いたまま変容させられたとき、住民に「奪われた」という感覚が生じる。ここでも、問題は国籍ではなく、空間や資源をどう扱うかという行動原理にある。
九評の最終章は、これらの遺伝子が「制御」に収斂すると論じる。
「遺伝子その九:制御——『党性』を用いて全党を制御し、国民や社会全体を支配する」
「『党性』は一貫した思惟パターンと行動パターンとして強化され、全国に普及した」
九評が描くのは、善悪の判断を個人から奪い、行動を定式化する統治である。この定式が長期にわたり社会に浸透すれば、国外に出た後も、その行動様式を再生産する可能性は否定できない。
倶知安の無届伐採は、「中国人だから起きた事件」ではない。九評が指摘するように、中国共産党の統治が形成してきた行動の型が、日本の法制度や地域社会と接触したときに表出した摩擦の一例と捉える方が整合的である。
だからこそ、日本社会に求められるのは感情的な非難ではない。手続きの厳格な適用、違反時の即時是正、説明責任を果たさせる制度運用であり、倶知安の森が突きつけているのは、外国人問題ではなく、異なる統治文化とどう向き合うかという現実的な課題だろう。
先ほど欺瞞の説明で「歴史的教訓として、共産党の承諾は信じてはならない、いかなる保証も実現しない」の後に続く言葉がある。それは「共産党を信じたら、命の保証はないのだ」ということだ。実際、中国共産党も中華民族、中国の伝統文化から発生したものではなく、もともとはマルクスから来ている。その証拠に中国共産党は政権を握ってから、世界のどの国、どの王朝も為したことのないような、何千万人もの中国人の大殺戮しているのである。






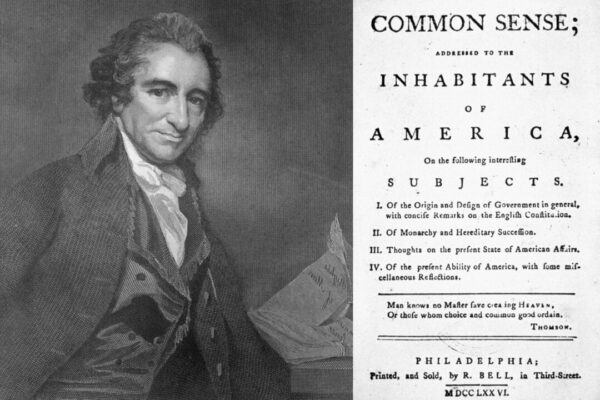



 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。