自民党の防災体制抜本的強化本部(谷公一本部長)は5月28日、政府が2026年度の設置を目指す「防災庁」について、石破茂首相に対し、首相直轄の組織とし専属職員を採用するなど体制強化を求める提言を手渡した。提言は、災害対応において他の省庁や自治体に対して指導や勧告を行える権限を持たせ、災害対策の司令塔機能を強化することが柱である。
提言をまとめたのは、自民党の谷公一氏ら「防災体制抜本的強化本部」のメンバーである。谷氏らは官邸を訪れ、石破首相に直接提言を手渡した。内容には、南海トラフ巨大地震などの大規模災害が迫る中、現行の内閣府防災担当では十分な事前防災機能や災害時の司令塔機能が果たせていないとの問題意識が示されている。
現状、政府は「防災庁」の設置に向けて、2024年11月1日、内閣官房に準備室を立ち上げ、準備を進めている。

提言では、防災庁を首相直轄の組織とし、専任の大臣を配置することを求めている。さらに、他省庁や自治体に対して指導・勧告権限を持たせることで、災害発生時に迅速かつ総合的な対応ができる体制を目指す。職員については、従来のように各省庁からの出向者だけでなく、防災庁独自の採用を行い、専門性を高める必要性が強調された。現状では、防災担当の多くの職員が国土交通省や総務省消防庁など他の省庁から一時的に出向してきており、2年ほどで元の省庁に戻るケースが一般的である。そのため、災害対応や防災行政の現場で得た知識や経験が組織内に長期的に蓄積されにくいという課題がある。
石破首相は提言を受け、「まったく異論はない。各省庁から来ては帰りでは経験を蓄積できない」と述べ、防災分野の専門職員を増やすことの重要性を認めた。今後は、志を持った人材が防災庁でキャリアを積み、専門知識と経験を蓄積できる仕組みづくりが期待される。
また、提言では防災庁内に「事態対処部門(避難所や仮設住宅の設置支援、救援物資の供給などを担当)」、「災害シミュレーションに基づく対策立案部門」、「人材育成や官民連携部門」、「会計や人事といった官房機能部門」の4部門を設け、それぞれ局長級の職員を置くことや、災害時の代替機能を担う地方拠点の設置も盛り込まれている。これにより、被災地の支援や物資供給、避難所運営、災害シミュレーション、人材育成など多岐にわたる業務を総合的に担うことを目指す。
防災庁設置の背景には、地震や台風など自然災害の激甚化・頻発化がある。専門性と迅速な対応力を持つ新組織の設立により、被災者支援や復興の質の向上が期待されている。
懸念される日中防災協力
一方、日本と中国は防災分野での協力を進めている。2025年2月には四川省で日中防災減災シンポジウムが開催され、地方自治体や専門家が参加し、地震対策や災害対応の知見を共有した。また、日中韓三カ国による防災担当閣僚級会合も定期的に行われている。
しかし、防災協力の拡大には安全保障上の課題も存在する。防災分野で共有される災害情報やインフラデータが、軍事やサイバー攻撃など安全保障上の目的に転用されれば、日本の重要インフラの脆弱性が露呈するリスクがある。中国側の防災機関は危機管理全般を担っており、情報の取り扱いには細心の注意が必要だ。さらに、サイバー空間や情報戦のリスクも高まっているため、政府や関係機関は情報管理や協力範囲の明確化、リスク評価を徹底する必要がある。
防災庁の設立と国際協力の推進は、災害大国日本にとって重要な取り組みである。しかし、国民の安全と安心を守るためには、情報管理や安全保障面でのリスクにも十分な配慮が求められる。



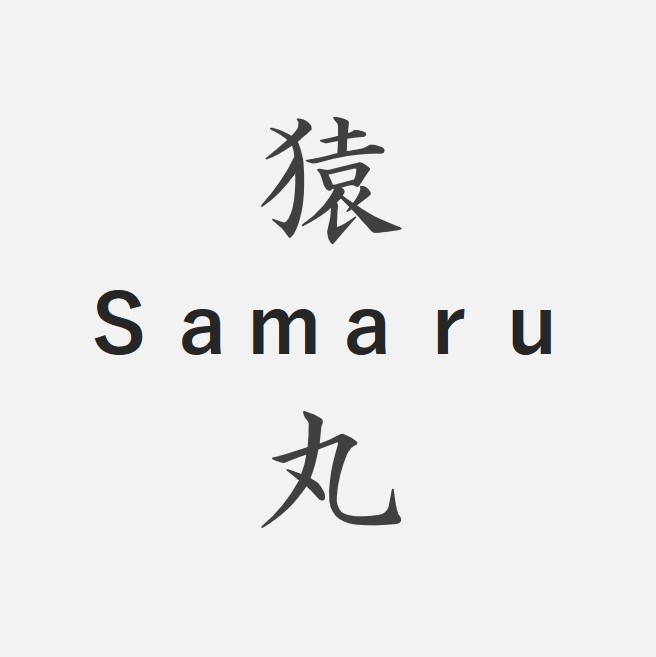






 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。