東京都板橋区のマンションで、中国人オーナーによる家賃の大幅な値上げと住民退去が相次いでいる問題を受け、片山さつき参院決算委員長(自民党)は6月9日の参院決算委員会で、外国人による居住用不動産購入に関する法規制の見直しを強く訴えた。
片山氏が取り上げたのは、同区内の中古マンションで発生した事例である。中国に住所を持つ人物がマンションを購入した後、家賃が相場の2倍から3倍に引き上げられ、住民の約3割が退去を余儀なくされた。中には、7階に住む70代の高齢女性に対し、エレベーターを停止させて退去を促すような行為も報じられている。このマンションでは、家賃が7万2500円から19万円にまで跳ね上がった住民もおり、既に5世帯が退去、さらに4世帯が退去予定とされている。
片山氏は「日本の弱い国民が常識が通用しない相手の強硬手段におびえている」と指摘し、外国人による不動産取得や民泊運営が地域住民の生活や安全に深刻な影響を及ぼしている現状を問題視した。また、区長からも「区ではこれ以上の対応ができない。国としての対策をお願いしたい」との要望が寄せられているという。
現行の日本の法律では、外国人による不動産購入に大きな制限はなく、日本人と同様に所有権を取得できる状況が続いている。ただし、2024年4月からは一部規制が強化され、国内連絡先の登録義務が課されている。しかし、現状では住宅用不動産の購入自体を制限する法律は存在しない。

こうした背景のもと、片山氏は「国民の生活の場が、外国資本の利益の場になってはならない」と述べ、外国人による不動産購入や土地所有、民泊運用に関する法制度の抜本的な見直しを求めた。これに対し、石破首相も「インバウンド消費は重要だが、国民の安全・安心が損なわれることは断じてあってはならない。誰のための政府かを問い直す必要がある」と応じ、関係省庁と連携して対策を徹底する方針を示した。
中国からの移民増加の背景
中国からの移民が増えている背景として、中国国内の政情不安や監視社会化の進行、そして米中対立の激化が大きな要因となっている。
まず、中国国内では中国共産党政権による民間企業への規制強化や厳しいゼロコロナ政策の再来のリスク、さらには政治体制への不安が広がっている。中国では当局による監視や抑圧が強まり、不都合な人物やその家族までが監視や移動制限の対象となる事例も報告されている。こうした監視社会化の進行や人権への懸念が、特に富裕層や知識人の間で国外移住の動機となっている。
加えて、米中対立の激化も中国人の移住先選択に影響を与えている。米国では中国からの移民が減少傾向にある一方、オーストラリアや日本など他国への移住が増加している。米中間の政治的・経済的な緊張が高まる中で、中国人がより安定した環境や新たなビジネス機会を求めて他国への移住を選択する傾向が強まっている。
日本政府は早急に移民や外国人に関連する政策を見直し、抜け穴を塞ぎ、国民の安全が守られる社会を構築し維持することが求められている。



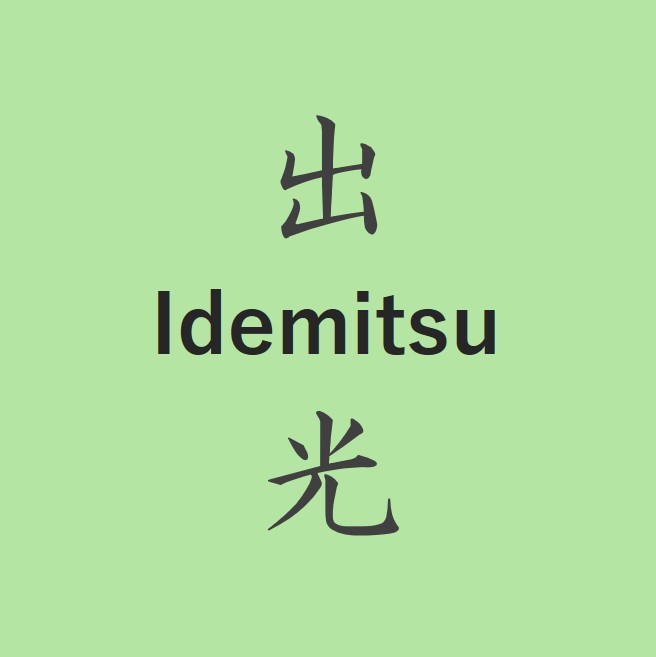






 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。