先週、中国共産党(中共)軍内で現役最高位の将軍、張又俠上将が、突如として失脚した。これは単なる高官失脚の一例にとどまらず、世界に改めて突きつけられた現実でもある。すなわち、共産独裁体制が最も恐れるのは外部の敵ではなく、「命令に従わない身内」だということだ。
共産体制において、軍隊は国家の軍ではなく、党の軍である。さらに正確に言えば、最高指導者個人の軍隊だ。権力の座を揺るぎないものにするための鉄則はただ一つ。軍権を自らの掌中に収め、それを骨の髄まで握りしめ続けることだ。
問題は、独裁者が好んで口にする「絶対的忠誠心」が、最も検証困難な概念だという点にある。今日忠誠を誓う者が、明日には反旗を翻さないと言い切れるのか。今はスローガンを叫んでいても、裏で別の計算をしているのではないか。その結果、独裁者が絶対的忠誠を求めれば求めるほど、心の平穏からは遠ざかり、疑心暗鬼と恐怖は深まっていく。そして最終的に、粛清を繰り返すことになる。
これは習近平個人の心理的問題ではない。共産統治そのものが内包する構造的論理である。スターリンから毛沢東、金正恩から習近平に至るまで、権力が集中すればするほど、周囲にはより低く跪くことが求められる。しかし、人々に絶対的な服従を強いれば強いるほど、今度はその服従が「真の服従なのか」という疑念が深まっていくのだ。
共産政権の核心は、最高指導者がすべての権力を独占し、党・国家・軍・警察のすべてが一人の命令に従う体制にある。だが皮肉なことに、どれほど独裁を強めても、自らの命令を実行に移すには高官や側近らの手に頼らざるを得ない。そして彼らが握っているのは、銃と兵権、情報、さらには軍事機構の運営能力なのだ。
ここに矛盾が生じる。
権力に最も近い人物ほど有能であり、同時に最も危険な存在でもある。
つまり、能力が高いほど脅威と見なされ、人望が集まれば集まるほどいつか「別の派閥を形成する」宿敵候補として警戒される。
その結果、独裁者は抜け出せない被害妄想に陥る。誰かが陰謀を企てているのではないか、表面上の忠誠を装っているのではないか、外国勢力と密通しているのではないか、そうした疑念に取りつかれる。そこで便利に使われるのが「外国勢力」というレッテルだ。通敵・売国のレッテルを貼れば、最も残酷な政治闘争を、最も愛国的な行為として正当化できるからだ。
この筋書きは、スターリンがすでに実践していた。1937年、ソ連赤軍の最も優秀な将軍の一人、トゥハチェフスキー元帥は、ナチス・ドイツと結託し、スターリン転覆を企てたとして告発された。罪状は虚偽だったが、それは重要ではなかった。彼は有能で、人望が高く、権力に近すぎた。彼が生きている限り、スターリンは安眠できなかったのである。
大粛清の時代、スターリンは特に「トロツキー派」を好んで摘発した。彼らは国際的なつながりや海外との関係を持ち、「外国の代理人」と断じやすかったからだ。ソ連の五人の元帥のうち三人を殺害した。残る二人が生き延びた理由はきわめて現実的だった。軍事的能力が低く、政治的脅威にならなかったからである。言い換えれば、強くないほうが安全だ。
中国も例外ではない。1949年以降、中共軍内では粛清が繰り返されてきた。その根底にある恐怖は一貫している。銃を握る者が、いつ銃口を最高指導者に向けるか分からないという恐れだ。
毛沢東時代、標的になったのは往々にして無能な人ではなく、「十分にひざまずかなかった者」だった。彭徳懐は、ソ連のフルシチョフに同調して大躍進や人民公社を批判しただけで、反党分子として、政治生命を断たれた。やがて毛沢東自身が後継者に指名した林彪ですら、クーデターを企てたとして告発され、謎に包まれた航空機墜落事故で命を落とした。
毛沢東の恐怖心は空想ではなかった。1964年の「マリノフスキー事件」以降、外国勢力が関与する軍事クーデターや政変は、もはや物語ではなく、現実の脅威だと彼は確信するようになったのである。
ソ連共産党は当時10月、無血クーデターによってフルシチョフを失脚させた。数週間後、周恩来と賀竜はモスクワを訪れ、フルシチョフ失脚後に中ソ関係が和解する可能性があるかどうかを探った。
その際、ソ連国防相のマリノフスキー、第二次世界大戦末期に中国東北部を制圧し、林彪およびその配下の共産軍と関わった経験を持つ中国通のソ連軍将領は、賀竜に率直にこう語った。
「中ソ関係を壊したのはフルシチョフと毛沢東だ。われわれソ連はフルシチョフを排除した。次は君たち中国人が毛沢東を排除すべきだ」
この言葉を聞いた毛沢東は激怒し、我を失った。この一言は、毛の心に生涯抜けることのない棘を突き刺すこととなり、中共党史における極めて重要な一頁となった。そして、その後の政治に巨大で破滅的な影響をもたらした。
皮肉なことに、毛沢東は側近が自分を陥れるのではないかという恐怖に取りつかれ、体制内で最も忠実だった劉少奇でさえ守ることができなかった。毛は劉を「裏切り者、内通者、労働者の敵」と罵り、身近に潜む第二のフルシチョフと断じた。劉少奇は文化大革命の中で苛烈な迫害を受け死亡した。共産政権の最も残酷な点はここにある。核心に近づくほど、死は早まる。
毛沢東は死去したが、この論理はその後も受け継がれ、暴力的な支配は少しも弱まらなかった。趙紫陽は職業軍人ではなかったが、同じ運命をたどった。彼は訪中したゴルバチョフに対し、中国は集団指導体制ではなく、「終身制の廃止」や「若い幹部の登用」を唱えながらも、実権を握っていたのは引退後も垂簾聴政を続けた鄧小平だと率直に語った。さらに天安門事件の際、中央軍事委員会副主席として武力弾圧の命令を出すことを拒んだ。この「非情さの欠如」と「正直すぎた」姿勢が、趙紫陽に政治的死刑を宣告する結果となった。
習近平時代になると、軍内の粛清は止まるどころか、さらに激しさを増した。2012年の就任以降、100人を超える軍高官が粛清され、その規模は文化大革命後で最大とされる。表向きは反腐敗だが、実態は政治的地雷除去に近い。習近平に近い人物ほど、危険度は高い。
中国では、中央軍事委員会副主席という地位は、全国で最も座り心地の悪い椅子の一つだろう。実権を握り、最高指導者に最も近い立場にあるため、その疑心暗鬼の吐息を、日々その至近距離で浴び続ける。1949年以降、9人の軍委副主席が粛清され、その多くが敵と密通したとの罪を着せられた。
習近平政権下では、引退したばかりの郭伯雄、徐才厚といった元副主席がまず失脚した。2023年には前例のない大粛清が起き、ロケット軍司令官、軍需調達の責任者、戦区司令官が次々と更迭され、最終的には習自身が抜擢した人物にまで及んだ。
2025年には何衛東と苗華も粛清され、そして今、張又俠の番が回ってきた。長年の盟友で、同じ太子党出身者である張まで排除されるとなれば、事態はさらに意味深だ。忠誠派すら粛清の対象となることは、習近平が悪人を探しているのではなく、「自分を不安にさせる人物」を探していることを示している。
注目すべきは、今回の件が共産政権における最も古く、かつ致命的なレッテル、通敵・売国へと発展する可能性がある点だ。張が核機密をアメリカに漏らしたとの告発が取り沙汰されている。先ほど述べたように、この種の罪名は政治的効果が極めて高い。「国家安全を守る」という名目で、最も露骨な権力闘争を、最も神聖な正義の行為に仕立て上げることができるからだ。
これが共産体制における粛清の究極的論理である。地位が高いほど、変節した裏切り者の烙印を押されやすい。この体制では、生き残れるかどうかは能力でも、人格でも、功績でも決まらない。ただ一つ、最高指導者の恐怖をかわし、目を付けられずに済むかどうかにかかっている。
独裁者にとって最大の脅威は、外敵ではない。最も近くにいて、最も銃の撃ち方を熟知している軍の指導者こそが、最大の脅威なのだ。
要するに、中共の軍内粛清は決して「反腐敗」ではなく、体制が自らを守るための制度的本能である。独裁者は国家を治めているのではなく、恐怖を管理している。強い軍を築いているのではなく、銃口が決して自分に向かないことを保証しているにすぎない。ルーマニアのチャウシェスクは、その点で十分に徹底できず、破滅を招いた。
これこそが共産体制の最も滑稽な点だ。自らを最も安定し、最も団結し、最も規律がある体制だと言い続けながら、常に「誰かが自分を陥れようとしている」という妄念の中で生きている。中枢に近い者ほど危険で、有能な者ほど排除されやすく、忠誠心の強い者ほど疑いの目を向けられる。
この政治論理のもとでは、張又俠が最後の犠牲者になることはない。次が現れても不思議ではない。
なぜなら、共産独裁において最大の罪とは、汚職でも無能でもなく、最高指導者を眠れなくさせることだ。
余茂春(Miles Yu)
国問題を専門とする米国の学者・政策研究者。元米国務省政策企画室(Policy Planning Staff)中国担当首席顧問
余茂春氏のXより転載







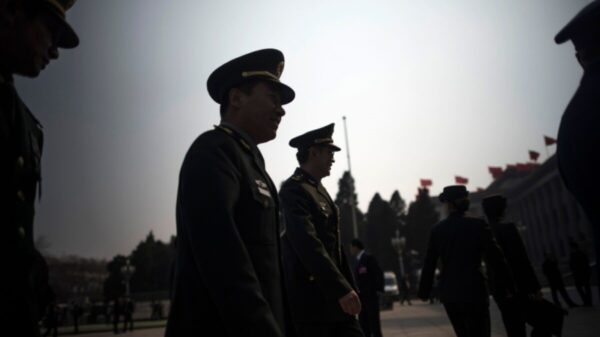
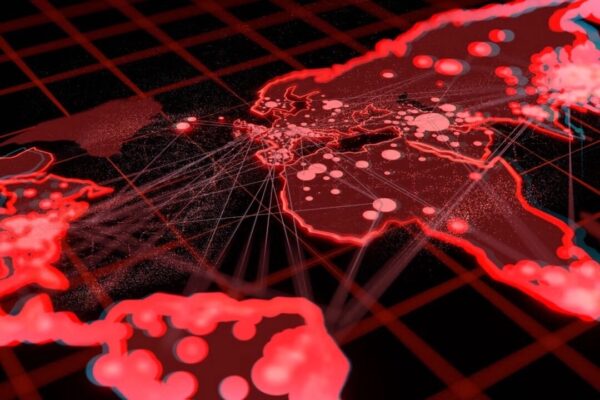

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。