米中間の関税戦争が長期化し、輸出が大きな壁に直面する中、中国共産党(中共)は「輸出商品の国内販売」を強力に推進している。だが、専門家や経済学者は、こうした政策が中国経済のデフレ危機をさらに悪化させると警鐘を鳴らしている。
デフレは中共が長年解決を目指してきた構造的な問題であり、投資銀行ゴールドマン・サックスも最新の報告書で、2025年の中国消費者物価指数(CPI)が0%まで下がると予測している。米中貿易戦争の短期的な解決は見込めず、中国経済は多くの課題に直面している。
米中貿易戦争と「輸出商品の国内販売」政策
現在、アメリカの対中関税は145%、中国側の対米関税は125%に達し、両国の貿易はほぼ断絶状態となっている。さらに、5月2日からアメリカは中国からの小口荷物に対する免税措置を廃止し、120%または1点あたり100ドルの関税を課すことになった。こうした輸出障害の衝撃を緩和するため、中共は「輸出商品の国内販売」を強力に推進し、民間消費を刺激しようとしている。
EC大手の京東やテンセント、抖音(TikTok中国版)などは、アメリカ市場向けだった商品を中国国内で積極的にプロモーションしている。京東はアメリカ向け商品を販売する特設エリアを設け、最大55%の割引を実施。大型チェーンスーパー「永輝超市」も輸出品専用エリアを設置し、上海では5日間の輸出カーニバルイベントが開催された。
デフレ悪化とデフレスパイラルの危機
しかし、多くの分析はこうした政策が中国経済のデフレ危機をむしろ悪化させると指摘する。輸出製品の大幅割引による国内転換は短期的には在庫処分やキャッシュフローの改善に寄与するが、長期的には各業界の価格決定力と収益力を弱め、コスト削減競争を激化させる。結果として、デフレの悪循環が深まる恐れがある。
実際、中国国家統計局のデータによると、2024年のCPIは前年比わずか0.2%上昇、工業における生産者物価指数(PPI)は2.2%下落となった。輸出用在庫の国内流入は過剰生産能力をさらに悪化させ、デフレ圧力が経済全体に波及している。政府による景気刺激策も限定的で、価格下落が続く中、企業や家庭は支出を控え、投資判断も慎重になり、成長の勢いが弱まっている。
ゴールドマン・サックスの予測と現場の実態
ゴールドマン・サックスの中国チーフエコノミスト、単輝氏は、今年の中国CPIが0%まで下がり、PPIも1.6%下落すると予測している。価格が下がらなければ、国内や他海外バイヤーがアメリカ向け過剰供給を吸収できず、製造業の生産能力は関税引き上げに迅速に適応できないため、過剰生産能力の問題がさらに深刻化する可能性がある。
モルガン・スタンレーも、貿易戦争の影響で輸出受注が減少し、PPIは4月に2.8%下落、3月の2.5%からさらに下落幅が拡大すると予測している。2023年と2024年の中国CPIは長期間ゼロ近辺で推移し、2025年2月と3月は2か月連続でマイナス成長となった。PPIも29か月連続で下落し、過去4か月で最大の下落幅を記録した。
企業現場での影響と価格競争の激化
イギリスのバークレイズ銀行の中国担当シニアエコノミスト、周英科氏は、大量のアメリカ市場向け割引商品が国内に流入することで企業間の価格競争が激化し、企業の収益力が圧迫されていると指摘する。雇用や所得の安定に対する懸念が消費需要を弱め、デフレ圧力が続く。
義烏のスポーツ用品工場「大陸オーケイ体育用品公司」では、米中関税戦争の影響で輸出受注が前年同期比60%減少。最も低価格のバレーボールは2022年には1個7~8元で売れていたが、2024年上半期には5.8~6元まで下落し、2年で20%もの価格暴落となった。
「輸出商品の国内販売」は一時しのぎに過ぎない現実
北京の投資銀行「香頌資本」取締役の沈萌氏は、中共の再販売支援策は一時しのぎに過ぎず、もともとアメリカ市場で高値販売していた輸出業者にとっては、国内販売は滞留在庫の処分や短期キャッシュフローの緩和策にしかならず、ほとんど利益が出ないと指摘する。利益圧迫は一部輸出企業の倒産を招き、他の企業も工場稼働停止を避けるため赤字経営を強いられる可能性がある。
ゴールドマン・サックスの推計では、中国にはアメリカ向け輸出品の生産に従事する雇用が1600万件(労働力総数の2%以上)ある。ユーラシア・グループの王丹氏も、最低免税政策の廃止とキャッシュフロー悪化が多くの中小企業を破産に追い込み、輸出依存地域の失業者数が増加、都市部失業率は今年平均5.7%に達し、政府目標の5.5%を上回ると警告している。
米中貿易戦争の長期化と中国経済の課題
ゴールドマン・サックスは最新報告書で、中国のマクロ経済が米中貿易摩擦の激化で多くの課題に直面し、2025年の実質GDP成長率は4.0%にとどまると予測している。中共は2025年の成長目標を「5%前後」としているが、米中双方の関税交渉には根本的な対立と高い不確実性があり、短期的な貿易合意の実現は極めて困難とされる。
中国は財政支出拡大による景気刺激の余地はあるものの、長期的な財政の持続可能性を考慮し、政策刺激の規模は慎重かつ選択的になっている。これまで中国経済のリバランスは緩やかに進められ、景気後退時にはインフラ建設や生産補助金に依存してきた。しかし、アメリカの関税が長期的に高止まりし、過剰供給が他国で吸収されない可能性を考慮すると、中国はより深い改革を加速する必要がある。
改革の方向性としては、地方政府に消費税徴収権を与えて消費を直接刺激すること、社会保障体制の強化による消費者信頼の向上、消費関連インフラへの投資などが挙げられる。中国経済は、出口が阻まれ内需転換を進める中で、デフレ危機と構造改革の課題に直面している。









 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




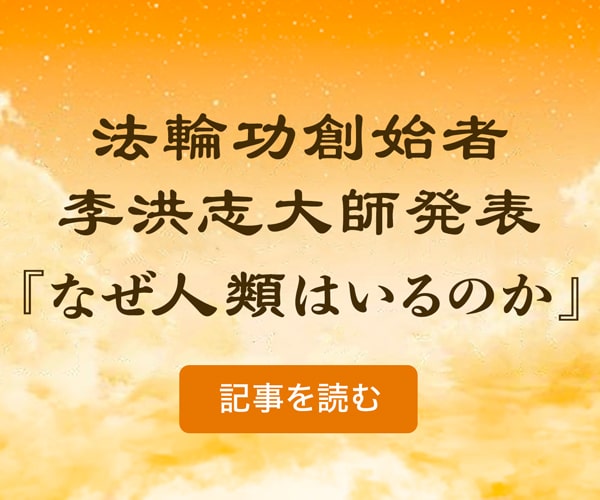
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。