3月、中国・安徽省の高速道路で、中国スマホ大手シャオミ(小米)製EV「SU7」がスマート運転機能の使用中に中央分離帯へ衝突・炎上し、女子大学生3人が命を落とすという重大事故が発生した。
その衝撃は広く波及し、事故現場付近の高速道路には「スマート運転は禁止」と明示する電子掲示板メッセージが相次いで登場。社会全体で「スマート運転」に対する警戒感が一気に高まった。
「スマート運転」とは、正式には運転支援システム(ADAS)を指す場合が多く、ドライバーがハンドルを握りつつ、一定の機能(車間距離の維持、自動ブレーキ、車線維持など)を補助的にサポートする技術である。
一方、「自動運転」とは、人間の操作を不要とする完全自律走行を意味し、システムが全責任を持って車を制御する。
そして5月4日、シャオミの公式サイトにおける「SU7」の新車予約ページの表記が静かに変更された。従来「スマート運転(中国語:智能駕駛/智駕)」という呼び名が、目立たぬかたちで「運転支援(中国語:輔助駕駛)」に書き換えられていたのだ。
一見はただの呼び名の変更。しかしネット上では「責任逃れのためのすり替え」と批判が噴出している。
「名前を変えれば事故の責任も消えるのか」「宣伝では“未来運転”と騒いでおきながら、いざとなれば“あれは運転支援機能でした”とは無責任すぎる」といった怒りの声が相次いでいる。
もちろん、肯定的に受け止める見方もある。「過熱した自動運転ブームにブレーキをかけ、現実とのギャップに向き合った英断」とする声や、「ユーザーの誤認防止になる」とする意見もあるのは事実だ。
だが、そうした「配慮」が本当に事故の前に必要だったのではないか。そもそも「スマート運転」という言葉で、メーカーはあたかも高度な自動運転が可能であるかのように誇張してきた。
それが今、問題が起きると“技術とユーザー理解のギャップ”と他人事のように語るのは、責任逃れにほかならない。
つまり、スマート運転はあくまで“運転補助”、自動運転は“無人での走行”を目指す技術であり、責任の所在も異なる。事故時に「手を離していた」か否かが議論を左右するのは、この違いに由来する。
近年、中国のEV広告ではこの線引きがあいまいにされ、「スマート運転」という語が、あたかも「完全自動運転」であるかのように使われていた。
そして今、名称を変えることで過去をなかったことにしようとしている。だが、事故で命を奪ったのは「名前」ではない。誤認を誘う宣伝の構造そのものである。





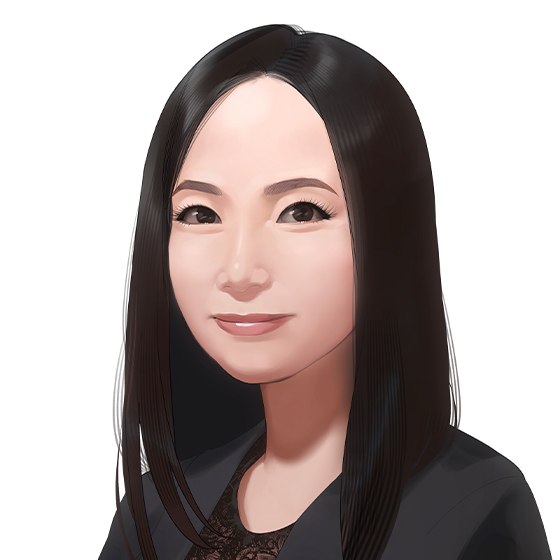






 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。