中国共産党(中共)は、ラテンアメリカ諸国との関係強化を加速させており、ここ数週間で複数の外交・経済協定を締結した。
今月初めに北京で開催された中国・ラテンアメリカ首脳フォーラムで、習近平は「政治、経済、安全保障の各分野で連携を強化し、ラテンアメリカ諸国と協力していきたい」と述べ、関係深化への意欲を示した。
また、現在のアメリカの通商政策を念頭に、「関税戦争や貿易戦争に勝者はいない」と強調。中国との貿易関係を、アメリカに依存しないサプライチェーンの多様化手段として提示した。
習はさらに、「中国はラテンアメリカ諸国と連携し、中国企業の投資を促進するとともに、クリーンエネルギー、5G通信、AIなどの分野での協力も拡大する」と表明した。
インフラ融資を通じた影響力拡大
この方針に基づき、中共政府はラテンアメリカおよびカリブ地域における経済的・政治的影響力を戦略的に強化する複数の施策を開始した。その柱となるのが、総額92億ドル(約1兆3千億円)規模の新たなインフラ投資向け融資枠である。
この資金は、過去の類似プログラムと比べるとやや規模が小さいが、中国経済の減速を背景にしながらも、地域全体への影響力を広げる動きと見られる。
特に注目されるのは、この融資がすべて人民元建てで行われる点だ。ラテンアメリカ諸国に米ドル以外の通貨で債務を抱えさせることにより、中国との経済的結びつきを強め、ドル依存を相対的に下げる効果がある。
コロンビア 中共主導の新開発銀行に加盟申請
この発表に続き、コロンビア政府は上海を本拠とする新開発銀行(NDB)への加盟申請を行った。同国は、アメリカの対外援助削減による財政圧迫への対応策を模索している。
コロンビアのグスタボ・ペトロ大統領は、同銀行による大西洋と太平洋を結ぶ全長約120キロの運河建設プロジェクトへの融資に期待感を示し、「コロンビアを南米とアジアの貿易の要衝に押し上げる可能性がある」と語った。
新開発銀行は2014年に、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ、いわゆるBRICSによって設立された。世界銀行や米州開発銀行など、米ドル主導の国際金融機関に対抗する位置づけである。
米サウスカロライナ大学エイキン校の謝田教授は、「今回の中国の投資は、パナマ運河に頼らずに大西洋と太平洋を陸路で結ぶ代替の越洋貿易ルートを構築することを狙っている」と分析。
「中共は依然として南米大陸を横断する鉄道や運河の整備を進めようとしており、これはパナマ運河を迂回する戦略の一環といえる。中国のグローバル戦略において重要な位置を占めている」と述べた。
一帯一路にコロンビアが正式参加
習近平とペトロ氏は今月、首脳会談を行い、コロンビアが正式に「一帯一路」構想に参加することで合意した。
一帯一路は、中共が主導するグローバルなインフラ整備構想であり、アメリカ政府はこれまで「途上国を債務の罠に陥れる」として繰り返し懸念を表明してきた。
コロンビアの参加により、中南米およびカリブ地域で同構想に加わっている国は23か国となった。アルゼンチン、ペルー、キューバ、パナマ、ベネズエラ、ウルグアイ、チリなどがこれに含まれる。
コロンビアのサラビア外相は、「今回の一帯一路参加は、わが国にとって数十年で最も大胆な外交的一歩だ」とコメントした。
中国はすでにアメリカに次ぐコロンビアの第2の貿易相手国であり、輸入元としてはアメリカを上回る最大の供給国となっている。
習は会談で、コロンビアからの輸入拡大や中国企業によるインフラ投資の拡大を支援する意向を示し、経済関係の一層の強化を表明した。
文化交流で影響力拡大
中共は経済面にとどまらず、文化交流を通じた影響力の拡大にも力を入れている。
中共外務省は5月15日、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、ウルグアイの国民を対象に、30日以内の滞在についてビザなしでの渡航を認めると発表した。措置は6月1日から1年間実施される。
この制度は、アジアや欧州の一部諸国との取り組みに続くもので、中共政府は経済の減速に対応すると同時に、国外での文化的存在感を高める狙いがあるとみられている。
さらに、今後3年間で中南米の政党関係者300人を中国に招待し、国家統治に関する「ベストプラクティス」を共有する方針だという。あわせて、政府奨学金3500件とさまざまな交流プログラムの提供も予定されている。
米中摩擦の中、中南米との貿易が急増
こうした一連の動きは、中国と中南米諸国との急速な貿易拡大という背景を伴っている。
米中関係の悪化により、アメリカ向けの中国輸出が減少する中、中共は他の地域との貿易拡大によってその影響を補ってきた。
2024年1月から4月までに、中国のアメリカ向け輸出は前年比21%減少したが、ラテンアメリカ向けは11.5%増加した。加えて、インド向けは16%増、アフリカ向けは15%増、ASEAN向けも11.5%増と、全体的に拡大傾向にある。
2023年には、中国と中南米諸国との年間貿易総額が初めて5千億ドルを突破。今後も成長が続くと見られている。
その要因としては、大豆や牛肉といった農産物の輸入が増加している点が大きい。これはトランプ政権下で発動された対中関税の影響を受け、中国がアメリカ以外の調達先への切り替えを進めた結果とされている。








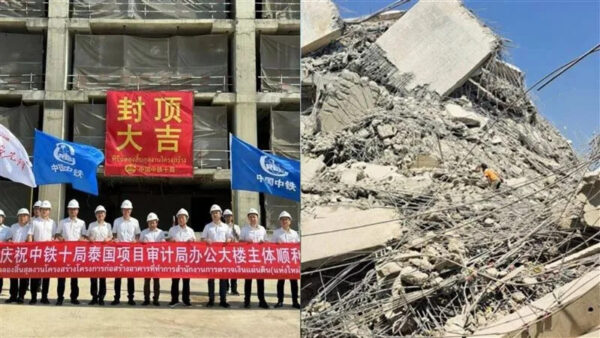

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




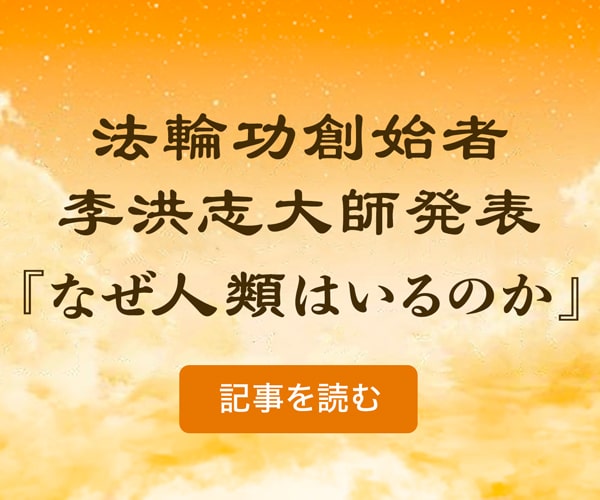
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。